 |
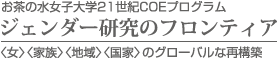 |
|
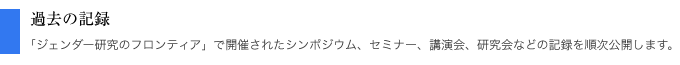 |
||||||
|
第5回研究会は、2004年3月に実施されたインドネシアとフィリピンにおける調査報告を目的とし、「国際移動とジェンダー(IMAGE)」研究会と合同で開催された。 前半のインドネシア報告では、まず平野がインドネシア女性の国際労働移動の現状について報告した。以下はその概要である。インドネシアで国際労働移動への一般 の関心が高まったのは、2002年8月に起きたマレーシアからインドネシアへの労働者送還事件を契機とする。送還された労働者への保護措置が問題視され、NGOや労働者側がインドネシア政府を提訴した。これはインドネシアでNGOが民法を拠り所として政府を提訴した初めてのケースとなった。次にインドネシア国際労働移動をとりまく現状だが、インドネシアは東南アジア第2位 の送出国であり、渡航地域としては、1960年代はサウジアラビアとマレーシア、1980年代以降はアジア地域が増加している。女性の国際移動のほとんどは家事・介護労働である。1970年代は「トランスミグラシ」(開拓移住)政策による国内労働移動が中心であり、1990年代より「移民の女性化」が顕著になった。さらに平野はインドネシア国際労働移動に関わる主体を4つに分類し、説明を行った。第一の主体は国家であり、関係省庁(労働・移住省、司法・人権省、外務省、内務省、社会省、国家教育省、保健省、宗教省、警察、女性エンパワーメント担当省)、BKPTKI(移住労働者配置のための協議体)、BP2TKI(BKPTKIへの助言を行う)、移民局、そして各国におけるインドネシア大使館があげられる。なお、インドネシアでは海外移住労働者に対する保護規定はない。第二の主体はPJTKI(インドネシア海外労働斡旋企業組合・海外出稼ぎ協会)であり、移住労働者に対する研修を行うが、実態は不明であるという。第3の主体はNGOである。具体例として、Solidaritas Perempuanは法的扶助や政策モニタリング、教育、移住先での組織化を行っており、またLBH-APIK(正義のためのインドネシア女性協会)は女性に特化して法的扶助を行っている。第4の主体は移住女性であり、雇用主による虐待、情報の欠如が大きな問題となっている。 さらに、熊谷がインドネシア調査における論点を提起した。第1に、下層におけるサーキュレーション、上層におけるフォーマルセクター参入という傾向がある農村から都市への移動と、海外移動との連続性である。また70年代以降の農業の近代化が、女性のフォーマルセクター参入や海外労働移動を促進していると考えられる。なお歴史的に見てインドネシア地域では国家成立以前から遠方への移動があったことからすると、現在では非合法の越境現象は、枠組みが変わったことによる非連続性・断絶であるとも考えられる。第二に海外労働移動における階層性であり、従来支配的であった国内移動に替わる新たな行き先かという点である。第3に、インドネシアの工業化により女性工業労働者が増加したが、国際労働移動とはどのように関連するのか。海外労働移動における人権問題と国内工場労働者の問題との連続性も考えられる。第四に、イスラム巡礼を支えるグローバルなシステムと、国際移動のシステムの関連である。第5に、80年代なかば以降の海外労働移動増加と、インドネシア国家による海外就労奨励策との関連である。最後に、ミクロレベルにおける女性の国際移動と主体形成では、家庭、イスラム、国家との関係はどのようであるのかが問われるだろう。 後半のフィリピン報告では、まず伊藤がフィリピンにおけるケア労働者海外派遣に関する政策と実態について報告を行った(調査メンバー:伊藤、足立、小ヶ谷、テネグラ、稲葉、越智)。今回の調査は、「アジアにおける国際移動とジェンダー配置」(F-GENS A2)における研究活動の柱のひとつである「再生産労働の国際移転とジェンダー配置」を背景とし、その目的とは、家事、育児、介護、看護などの分野におけるフィリピンからの海外出稼ぎ、特に”caregiver(ケア労働者)”派遣の実態と政策の展開、およびフィリピン国内における”caregiver”の需要に関する把握である。フィリピンに見られる再生産労働の国際移転は、海外にケア労働者を派遣する一方、国内への外国人高齢者受入という2つの局面 で展開していることが特徴的である。日本では少子高齢化による高齢者ケアの問題浮上と、国内のジェンダー再配置が関連しており、ここにフィリピンのケアの現状を研究する意義がある。伊藤は、調査を通 じて浮上した問題として、80年代以降女性の国際移動が増加しているフィリピンではdomestic helper、nurse、caregiverという職種が存在し、中間的位置にある”caregiver”の概念規定の難しさ、およびフィリピン人にケアの素質があるとする官民に共有された言説の関与を強調した。フィリピン海外雇用庁統計によると、”caregiver”の海外派遣数は1万9千人であり(2003年)、domestic helperより少ない。受入国は台湾、イスラエル、カナダが上位を占める。フィリピンでは、”caregiver”育成ビジネスがはやっているが、フィリピン海外雇用庁は、ケア労働者への「需要は期待されているほど大きくない」と見ている。ケア労働者の需要が期待されるのは台湾、イスラエル、イギリスであり、渡航先としてもっとも好まれているカナダは実際は2.2%にすぎず、米国と日本についても可能性は限定的としている。引き続き小ヶ谷が、TESDA(技能教育技術開発庁)での聞き取りから、フィリピン政府によるケア労働者(caregiver)の技能認定・要請の取り組みについて報告した。TESDAは労働雇用省の附属機関であり、海外労働者に限らずにフィリピンにおける労働研修規定を策定し、民間業者によるプログラム認定とチェック、修了者への認定書発行を行う。フィリピン政府によると、「caregiverはクライアントの家庭、あるいは施設で、ケアを必要とする人への、パーソナルケアやサービスの提供を行う」と定義され、ケアの対象として子ども、高齢者、特別 要支援者が設定され、在宅あるいは施設(病院)での就労を想定した育成という立場がとられている。”caregiver”に必要とされるコンピテンシーは12に分類され、各々内容が詳細に定められている。ヘルスセクターにおける専門性という点から見た”caregiver”は、研修規定がない「家事労働者」(domestic worker)と、専門教育がなされ在宅より病院勤務を基本とする「看護師」(nurse)の中間的位 置と考えられる。次にテネグラがフィリピン女性大学(PWU)における”caregiver”研修プログラムについて、内容を具体的に報告した。最後に足立が「《優雅なる》退職生活あるいは高齢者《輸出》」と題し、フィリピンにおける日本人高齢者介護施設の現状報告を行なった。足立は、高齢者受入と国内投資としてのドル預金制度との関連、高齢海外移住者における社会経済階層という論点を提起した。フィリピン報告のまとめとして伊藤は、海外雇用庁というナショナルな水準と、ILOという国際水準の関連、および後者を意識するNGOや民間業者の動きとの関連について注意を喚起した。コメントは以下の通 りである。インドネシアの状況はフィリピンと比較し政府と民間の役割区別が不明瞭である、両国とも国が労働力を商品として輸出している、フィリピン人にケアの素質があるとする言説と外貨獲得政策との関連性、看護師・caregiver・家事労働者という区分と社会階層の関連、海外へのケア労働移動における「矛盾した」階層移動の可能性など。 |
||||||
| COPYRIGHT © 2003-2008 OCHANOMIZU UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED. このサイトについて |