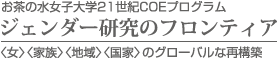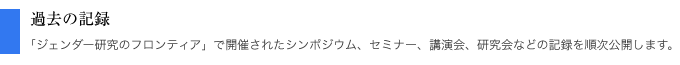【企画】プロジェクトD英語圏「英語圏ジェンダー理論/表象」研究会
【タイトル】Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of
"Sex"を読む
【司会・報告】竹村和子(お茶の水女子大学)
【報告者】(報告順・敬称略)
吉川純子(武蔵大学・COE客員研究員)
清水晶子(中央大学)
越智博美(一橋大学・COE客員研究員)
松尾江津子(お茶の水女子大学・博士課程後期)
加藤貴之(清和大学)
高橋愛(お茶の水女子大学・博士課程後期)
大池真知子(広島大学)
【記録】大池真知子・井川ちとせ
【日時】2004年3月19日14:00〜18:30
【場所】人間文化研究科棟6階大会議室
【備考】使用言語は日本語、出席者58名(学内+学外)
写真はこちら
|