 |
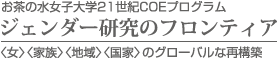 |
|
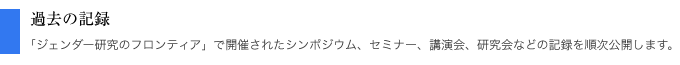 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
第1部:パフォーマンス 第3部:壇上対談 イトー・ターリによるパフォーマンス「Rubber Tit」は、会議室から机や椅子を運び出してつくられたスペースで行われた。そこでイトーは、床に座る観客を前に、いっぱいに膨らまされた巨大な「ゴムおっぱい」(Rubber Tit)を用いて様々なアクションを見せる。同時に、会場に設置されたスクリーンには、レズビアンであることをカミングアウトする政治家の映像(音声は日本語、字幕は英語)が流されていた。さらにイトーが「ゴムおっぱい」を観客の中に投げ入れることによって、観客はその手触りや匂いを直接的に体験する。30分ほどの間に、様々なインターアクションが引き起こされたパフォーマンスであったといえる。
後半では、フロアを交えての質疑応答が行われ、主に、イトーがパフォーマンスの「場」をどのように考えているのかという点に関心が集まった。このやりとりの中で明らかにされたのは「観客」を含めた「場」に対して、イトーの側から条件として望むものは何もないという姿勢であり、それは事前に行われた「ゴムおっぱい」のパフォーマンスに通じているものであることが、改めて覗われた。さらに、セクシュアリティに関する質問も寄せられ、竹村、イトーの二人が次のように語る場面もあった。
対談の最後は、次のようなやりとりで締めくくられた。
約40分という短い時間ではあったが、パフォーマンスの後に直接話しを聞ける貴重な機会であることに加え、「観客と同じ位置に」というイトーの姿勢がそのまま対談にも反映され、話し手の2人とオーディエンスとの距離が非常に近く、充実した、かつ笑いに満ちたひと時であった。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| COPYRIGHT © 2003-2008 OCHANOMIZU UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED. このサイトについて |