 |
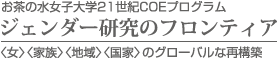 |
|
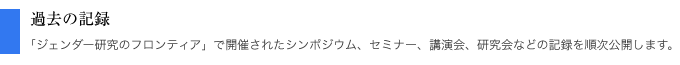 |
|||||||
|
【内容】 第1時間目は、人文地理学の立場から若林講師によって、東京大都市圏における30歳代シングル女性の居住地選択における研究を例に、国勢調査等の統計データやインターネット調査データの統計解析といった量的研究法と、グループ・インタビュー、個人インタビュー、広告、雑誌、ノンフィクション作品の内容分析を行った質的研究法の具体的な紹介がなされ、異質な資料や方法を使って多面的に対象を捉えた分析結果と、その研究方法のそれぞれの利点と限界について述べられた。 第2時間目は、臨床心理学の立場から大森講師により、臨床心理学におけるいくつかの研究手法、事例研究と事例報告の違いや、質的研究法や実証に基づく実践がアメリカでは最近重視される方向にあること、ただし教育プログラムにおいてはそれらのカリキュラムが非常に少ないこと等が紹介された。また単一研究において質的・量的データを同時または逐次的に収集する多元的方法デザインについての説明、さらにはとくに臨床心理学における実践と研究における研究者の利益とコスト、リスク及び協力者の利益の方向性や、質的研究プロセス、執筆における注意点などについても述べられた。 第3時間目は、社会学の立場から杉野講師により、量的研究・質的研究という区別が明らかにできるのかどうかといった問題提起や、社会学の中での計量分析のいくつかの考え方の紹介がなされた。また量的・質的研究のどちらかに相当するといった判断が難しい手法の具体例や、調査結果の形式化や標準化、コーディング、何がケースかといった検討すべき問題が挙げられた。さらに、ソフトウェアを使ったコーディングの例も紹介された。 3人の講師による講義の後行われた総合討論では、参加者からの質問や感想を踏まえ、それぞれの立場からの議論が繰り広げられた。
|
|||||||
| COPYRIGHT © 2003-2008 OCHANOMIZU UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED. このサイトについて |