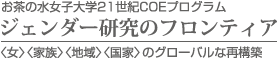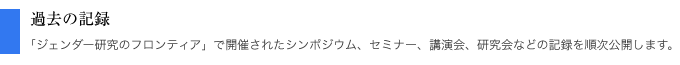|
�@

�Z�b�V����1�@���A�W�A�ɂ�����i�V���i���Y���ƃ��_�j�Y��
�L�^�F�쌴�ː���i�����̐����q��w��w�@���m����ے��ACOE�������j�@
�y���\�ҁE�^�C�g���z
�������i���ϊّ�w�j
�@�u�����Ȃ��҂̎����\�\�A���n���؍��̏����ɂ����ꂽ�j���m���l�̎��Ȓ�`�ɂ��āv
�r�����q�i�����ّ�w�j
�@�u�鍑�̃��}���X�w�O�ԁx�\�\�w�}�_���E�o�^�t���C�x�wM�E�o�^�t���C�x�w�~�X�E�T�C�S���x�v
�I�K�����i���ԏ��q��w�j
�@�u���؎Љ�̒��̓��{�R�q�Ԉ��w�r���ƒ����ƓI�����̘A�т̉\���v
�]�V�����i�����̐����q��w�@���m����ے��ACOE�������j
�@�u��������̃��t�@�G���O�h��`�\�\D.�EG�E���Z�b�e�B�́w���W�x��e�̔w�i�v
�y�R�����e�[�^�[�z
�@�A�q�j�i���ԏ��q��w�j
�@��K�݂ǂ�i��t��w ���_�����j
�y�i�@��z�r�c�E�i��t��w�j
�y���@�l�z�g�p����͓��{��E�؍��ꡎQ���� 169���B
�ʐ^�͂�����
�y�T�@�v�z
�@
�{�Z�b�V�����́A19���I�I�Ղ���21���I�����ɂ����āA���A�W�A�̐l�X�̃A�C�f���e�B�e�B�\�z�ߒ��ɂ����āA�Q�Ɠ_�Ƃ��Ă̏�����W�F���_�[�����ꂽ�����\�ۂ��A���l�ȃ��f�B�A�ɂ����Ăǂ̂悤�ɑn�o����A���邢�͏�������Ă����̂��������A���̔w��ɂ�������������j�I�Ȍ��͊W�₻�̍�p������������̂ƂȂ����B
�@
������́A1920�N��O���ɋN�������؍��ߑ㏬���̕ω����A�A���n�؍��̒j���m���l�̎��Ȓ�`�̖��Ƃ��Ę_�����B�u���O�͒N���v�Ɩ����A���n�؍��̒j���m���l���A���w�K���Ə������A�A���n�̖����I�Ȍ������\����ے�I�ȕ\�ۂƂ��Ĕ������邱�Ƃɂ���ăA�C�f���e�B�e�B�̓��h���������悤�Ƃ���l�����A���z�̏����w�ݍΑO�x�i1924�j�Ɍ����B�܂��A�j���m���l�̎����S���������ɖ����������@�Ƃ��āA���̌㉺�w�K���̏�������l���Ƃ��鏬���������o�ꂵ�Ă������Ƃ��w�E�����B
�@
�����āA�r�����q�́A�v�b�`�[�j�̃I�y���w�}�_���E�o�^�t���C�x�i�~���m����1904�N�j�A���㌀�w�l�E�o�^�t���C�x�i�u���[�h�E�F�C1988�N�j�A�~���[�W�J���w�~�X�E�T�C�S���x�i�����h������1989�N�A�u���[�h�E�F�C1991�N�A����1992�N�j�Ƃ����O�̃e�N�X�g�Ə㉉�̃R���e�N�X�g��ʂ��āA�i�V���i���Y���A�l���`�ƃW�F���_�[�̌�������鍑�̃��}���X�w�}�_���E�o�^�t���C�x���ǂ̂悤�ɕϗe���邩�l�@���A�鍑�̃��}���X��21���I�̃O���[�o���ȕ������{�Ƃ��č��Ȃ��͂𑝂��Ă��邻�̃w�Q���j�b�N�ȗ͂̍쓮���������B
�@
�����I�K�����́A���{�R�u�Ԉ��w�v������������V�����]���_�����o�����߂̒����ƓI�A�щ^���̈�ł���u2000�N�������ې�Ɩ@��v�����グ���B�قȂ閯���I�o���ƍ��ƃA�C�f���e�B�e�B�����W�F���_�[�����ꂽ�����̍\�����ł��鏗�����A�����ƓI�ȘA�т̎����̒��łǂ̂悤�Ȋ������o�������̂��A�����Ċؓ��̉^����̂����ꂼ��ǂ̂悤��2000�N�@���]�����A���̌�̊����𑱂��Ă���̂��ɂ��ĕ��A�u����̈Ⴂ�v�Ɋ�Ղ�u���A�т̏d�v�����w�E�����B
�@
�Ō�ɁA�]�V�����́A1890�N�㒆������1900�N�㏉���ɂ����āA���{�̖��Ԃɂ�莄�I�ɐ��i���ꂽ���t�@�G���O�h�̎��l����Ƃ�Rossetti��e�̔w�i�ɂ��čl�@�����B���t�@�G���O�h��`���ٕ����ɑ��鋤���I���Î�ɗR�����靘�����������ƁA����̂ɂ��̎��I��e���A����{�鍑�̖ڎw���A���n��`�ɑ��ًc����������̂ƂȂ蓾�����Ƃ��w�E���A���ꂪ���I�푈��̃i�V���i���Y�����g�̒��ŕ��ȍ��Ǝ�`�ɉ������Ă����l���𖾂炩�ɂ����B
�@
�ȏ�4�̕��A�A�q�j�́A���A�W�A�̖��Ƃ́A���Njߑ�ɂ�����A���n��`�̖��A������`�̖��ɂ���Ƃ�����g���m�F������ŁA�e�҂Ɏ��̂悤�Ȏ���������B
�@
������́A�A���n���؍��̏����ɂ����āA�j���m���l��������ʂ��đ��҂Ƃ��Ẳ��w�K���A�܂��͏�����ݒ肵���Ǝw�E�������A�����I�Ɍ���Ƒ��l���������҂�`�����ɁA�m���l�����͂ǂ̂悤�ȃW�����}�ɂԂ���A������ǂ̂悤�Ȑ헪��p���Ď��ʂ����Ă������̂��B�r�����q�́w�}�_���E�o�^�t���C�x����w�~�X�E�T�C�S���x�ɂ�����ߒ��̒��ŁA�������@�����L���Ȃ�������̒��ɗl�X�ȃo���G�[�V����������ϗe������Ǝw�E�������A���ꂪ���������̂��A�Ⴆ�w�~�X�E�T�C�S���x�ʼn���I�ȑ��݂Ƃ��ĐV���ɍ��グ��ꂽ�N���X�ɂ��ĂȂǁA���������ڂ������������B�I�K�����́A�؍��Ɠ��{�̏����̗���̈Ⴂ�𖾂炩�ɂ��A����̈Ⴂ�ɗ��r����Θb�ƗZ������������A�����ƒ��łԂ����Ă����ɂɂ��ċc�_���ׂ��ł͂Ȃ����B�܂��A���{�̏��������Q���̍����Ƃ��Ă̐ӔC�����邱�Ƃ����Ƃɕ������邱�ƂɂȂ���Ƃ����_�ɂ��Ă��������������K�v���낤�B�]�V�����́̕A�������Ƃ��đ�ϖʔ����w�E�����A�鍑�̋K�͂����܂�ɂ����������Ă���̂ł͂Ȃ����B�鍑�̋K�͂Ƃ́A�����I�ȉ��Î�`�����ׂē����悤�ȍL�͈͂ȃC�f�I���M�[�ł���A���̓����ɂ͑����̕������L���悤�Ƃ���ӎ���������Ă���B
�@
������K�݂ǂ�́A�e�҂Ɏ��̂悤�ɏq�ׂ��B������̕ɂ������w�ݍΑO�x�́A�鍑���{�ƐA���n�؍��̂���������������؍��m���l�j���̃A�C�f���e�B�e�B�E�N���C�V�X��`���Ă���B�ނ͒鍑���{����A���n������܂Ȃ������邪�A�ߑ㉻���ꂽ�؍��l�Ƃ��Ď��Ȃ��A�C�f���e�B�t�@�C���A�؍��̏����Ɖ��w�K�����A���傤�ǒ鍑���{���A���n�������悤�Ɍ��Ԃ����ƂɂȂ�B�r�����q�̒鍑�̃��}���X�ɂ݂�A�鍑�͒j���A�A���n�͏����Ƃ����X�e���I�^�C�v�͒f�łƂ���100�N�ȏ㑱���Ă���B�Ȃ��Ȃ�Β鍑��`�͂܂������Ă��邩�炾�B����w�l�E�o�^�t���C�x�͔��ɔ���ȃp���f�B�ŁA�A���n�̏����Ǝv�����̂����͒j�ł������Ƃ����̂́A�����̐A���n����̓Ɨ��̃��^�t�@�[�Ƃ݂�Ɣ��ɖʔ����B�I�K�����̕���́A������Q�҂��̐A���n�I�ȋ]���̑�\�Ƃ��Ă݂鍪�[���؍��̖��������ƁA���Ɩ\�͂̔�Q�҂ł���A���̍��Ƃ̈���ł�������{�l�����̃W�����}��������ɂȂ�B�u�Ԉ��w�v����鍑��`�I�ƍ߂Ƃ��Ă��̑��̂�����ʓI�Ȑ��\�͂����ʂ������A���߂Ē鍑��`�ɔ����钴���ƓI���ʔF���Ƃ������̂��o�Ă���̂ł��낤�B�]�V�����́̕A�鍑��`�ƐA���n�̕����`���̖��ɑ}�����邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��Ȃ烉�t�@�G���O�h��`�Ƃ͌Ñ�̕����ł͂Ȃ��A�s���I�����̊��S�Ȕے�Ƒޔp������ł���A�鍑��`�͂��̓����Ɍ|�p�̑ޔp�ݏo���Ƃ����������������_�������[���B���{�́A���邢�͏�c�q�̕s�K�́ARossetti�̂悤�ɑޔp�ł��Ȃ��������Ƃɂ���B
�@
���̏�Ŏ�K�́A�鍑��`����̕����̓����Ƃ��āA���m�̐l��I�E�����I�D�z���̎����A�A�W�A�A���n�ł́i���{�������̐�ɒu���j�ߑ㉻��`�ƃi�V���i���Y���A���{�ł́i���m�������̐�ɒu���j�ߑ㉻��`�ƃi�V���i���Y���̎O�������A�����̐�͈���Ă��A���l�̒鍑��`�ƐA���n��`�̘g�g�݂̒��Ő��܂ꂽ�����ł���ƌ��_������Ȃ��Əq�ׂ��B
�@
���̌�A�҂ɂ�郊�v���C���Ȃ��ꂽ�B������́A�w�ݍΑO�x�쒆�����̑��l���ɐG��A�܂��A�j���m���l�̎�l���ɂƂ��āA�����́A�l��I�E������`�I�ȕ\�ۂ���E���邱�Ƃ��ł��郁�g���|���^���Ƃ��ċ@�\�������Ƃ����������B�r�����q�́A�w�~�X�E�T�C�S���x�̊ϋq�_�̕K�v���ɐG��A�w�l�E�o�^�t���C�x���I���G���^���Y���ƃW�F���_�[�̓Η��̘g�g�݂�����������̂ł��邱�Ƃ��m�F������ŁA�|�s�����[�J���`���[�ɂ������R�I�ȓǂ݂ɂ��čl���Ă��������Əq�ׂ��B�I�K�����́A�������Ƃ��ߋ��ɂ��Ă̐ӔC���Ƃ邱�ƂƁA�������g�̌l�Ƃ��Ă̐킢���ꏏ�ɘ_�c����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Əq�ׁA�݂��̉^���ɂ��đ��ݕ]�������邱�Ƃ��^���̎����ׂ̈ɕK�v���Ɖ������B�]�V�����́A�����I���Î�`���ߋ��́A���邢�͑����̕����ɑ���[���،h�̔O�ł��邱�Ƃ��m�F���A�܂��A��c�q��Baudelaire����Ƃőޔp��\�����悤�Ƃ������̂́A���̕\���̎d���ɖ�肪�������̂ł͂Ȃ����Əq�ׂ��B�Ō�Ɏi��u���O�͒N���v�Ƃ����₢�����������Ă��邱�ƁA�����ɓ����͊W�ɂ��čl���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��m�F���āA�Z�b�V�����͏I�������B
 |
�Z�b�V����2�@���������̕ϗe
�L�^�F���x�ޕێq�i�����̐����q��w��w�@���m����ے��ACOE�������j�@
�y���\�ҁE�^�C�g���z
�����q�i�����̐����q��w�j�u���ƂƏ��w���\�������q�����t�͊w�Z������Ƃ��ā\�v
���p�P�i���ԑ�w�j�u�A���n���N�̋ߑ�ƕ��������͂̂��߂̃m�[�g�\�}�N���\����`���@�_�̒T���𒆐S�Ɂ\�v
�V��m���i�����̐����q��w�j�u�������̃t�F�A���[��e�[���\������p�ɂ�����l�`�������V�k�\�v
��玟姃�i���ԏ��q��w��w�@�C�m�ے��j�u�u�������v�̎���\1920�N�ォ��1930�N��ɂ����鏗���u�������v�����𒆐S�Ɂ\�v
�y�R�����e�[�^�[�z
�����؉��q�i������w�j
���K�a�i���ԏ��q��w�j
�y�i�@��z�z�q�����i�ꋴ��w�j
�y���@�l�z�g�p����͓��{��E�؍���B�Q���� 169���B
�ʐ^�͂�����
�y�T�@�v�z
�@
�Z�b�V����2�́A��L4���̔��\�҂�2���̃R�����e�[�^�[����A�����ɏ����̕����\�ۂ̕ϗe�A���邢�͂���ɑ����e�����̕ϗe�ɂ��锭�\���Ȃ��ꂽ�B���߂ɐ����q�́A�������{�ɂ����鏗���̍������ւ̃v���Z�X���ǂ̂悤�ɐ����i�߂�ꂽ�̂��ɂ��āA����ɏœ_�����āA�������q�����t�͊w�Z�i�����̐����q��w�̑O�g�j�ƍ��ƂƂ̘A�ւ��疾�炩�ɂ����B���͕��͂ɂ������āA�����V�c�c�@���q�i�����c���@�j�A���璺��A�����푈�̎O�_�Ɠ������q�����t�͊w�Z�Ƃ̉e���W���Q�Ǝ��ɍl�@�����B���Z�́A���q�c�@����̓I���f���Ƃ��āu���璺��v��M�A�V�c���Ƒ����Ǝ�`��S����������҂��A���{����ђ��N�֕��C�����Ă�������ŁA�u���璺��v�Ɋ�Â��ǍȌ����`����傫����E����悤�ȗD�ꂽ�l�ނ�y�o���Ă������B���Z�̑��Ɛ��������A�������t�Ƃ��Ăǂ̂悤�ȃW�����}������A�ǂ̂悤�ȋ�����s���Ă����̂���₢�����A�����ɂƂ��Ắ��w�⁄�̐^�̈Ӌ`�𖾂炩�ɂ���K�v������ƌ��_�t�����B
�@
���p�P�́A���N�ɂ����鏗�������͂��邳���̐V���ȗ��_�I�g�g�݂�����B���͂܂��A���݂̊؍��w��ɍ������̂���u�����v��O��ɂ������j���q��ᔻ�I�ɏȎ@���A�V�����䓪�����E������`�I���j���q���W�F���_�[�����w�ƘA�ւ����Ę_����B�A���n�����͐A���n����̖�����`�����łȂ��ƕ������\���ɂ���Ă���d�ɕs��������Ă����B���́A�ޏ������̗��j���ɂ������A�A����`�A������`�A�ߑ㐫�A�n���I�w�Q���j�[�ɉ����ăW�F���_�[�̎��_��ڍ������u������I���͕��@�_�iconjunctural analysis�j�v����A���w�I�ŕω��ɕx�A���n�̎���Ԃł́A�V���ȏ��������̕��͕��@���Љ���B
�@
�����ēV��m�����A20���I������p�ɂ�����l�`�⏭���̕���̕ϑJ�Ǝ�e�̕ϗe���Ƃ肠���A�����A�[�e�B�X�g�̎�ɂ�邢���鏗���������čl�����B�n�������j�����ƌ��ѕt�����Ă������m���p�̓`���I�Șg�g�݂ɂ����āA�j����Ƃɂ��l�`�⏭���̕��ꂪ�嗬�̔��p�����Ƃ��Ď�e����Ă����B����������ŁA������Ƃɂ�邻���̍�i�͎�|��玙�Ƃ������������̉����Ƃ��Ď嗬�|�p����͋�ʂ���A����������Ă����B�V��́A1920�N��ȍ~�̏�����Ƃ̐l�`�⏭���̕�����čl�@���A�ޏ����������ۂɂ̓w�e���Z�N�V���A�����x�ɂ�����W�F���_�[��Z�N�V���A���e�B�\����g�̊ς��̂��̂�ɗ�ɔᔻ�A�h��������̂ł���Ƃ��ĐV���Ȕ��p�j�ς����B�Ƃ��Ƀt�F�e�B�b�V��������A�����Ă��������̐g�̂��A�V�k�ƈ�̉������Ċh���I�ɕ\�ۂ����A��Ȃ��݂�̍�i���͂́A�V��̔��\�m�ɘ_������̂ł������B
�@
�Ō�ɁA��玟姃�ɂ��A���������Ƃ��Ă܂��̌n������\���ɂ���Ă��Ȃ��A1920�N�ォ��30�N��ɂ����Ă̊؍��́u�������v���������ꂽ�B�����I�S�̐���オ���������1920�N��̊؍��́A�����ɐV���ȁu�����v�̍�@�A�܂�u�v���g�j�b�N�v�ȉߒ����d�v������A�u���̓I�ȔM��v�͌���ւƖ��U����Ă����B���̌X���͏����m�̈��Ɋւ��錾���ɂ����Ă͂߂��A�ޏ��������u�~�]�����́v�ł���A�h���I�ȑ��݂ł��������Ƃ�E�F���Ă��܂��Ă����B�Ԃ́A�����́w��������x��w�V�����x�Ƃ������V����G���ɕ\�ۂ��ꂽ���������������Ă�����[���Љ�Ȃ���A�����������̕����̐V���Ȏ�e���@��͍����鎎�݂�����B
�@���ɁA��l�̃R�����e�[�^�[����ȉ��̂悤�ȃR�����g���q�ׂ�ꂽ�B���߂ɏ����؉��q����A��L�Z�b�V�����S�̂�ʂ��Ă̕�I�ȃR�����g����ꂽ�B�����́A�����q�A�V��m���A��玟姃�̔��\���A���ꂼ�ꍑ�ƁE�����̂ɂ����鏗���̐g�̂Ƃ������^���x����_�������́A�l�`���p�ɂ��\�ۂƂ������ԃ��x���A�u�������v�����ɕ\�ۂ��ꂽ���g�̐g�̂Ƃ����l���x���Ƃ������A3�̃��x������̔��\�ł���A����ɁA���p�P����͗��_�I�A�v���[�`������A���Ƀo���G�e�B�ɕx�݂Ȃ�����o�����X�̎�ꂽ�Z�b�V�����ł������ƕ]�������B���̏�Ŋe���\�ɑ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ��B���p�P�̔��\�́A�x�z�E��x�z�̍\��������ł̒����ƓI���f���������̂ŁA���j�������ŏ]���ʼn߂���Ă����������[�U���闝�_�ł������B��玟姃�ɂ��E�������ꂽ�u�������v�ւ̔��́A�嗬�̕��������̒��ɘc�Ȃ��đ̌n������Ă��܂����Ƃ̊댯���ɉ����A���̑̌n����R��o��悤�Ȏ��Ȃ̗]����ǂ̂悤�Ɉ�����悢���Ƃ��������������̂������B����ɐ����q�����ƂƂ����g�̂ւ́u�������v�̗��p�𖾂炩�ɂ������Ƃ��āA�����̂ɂ���߂Ƃ�ꂤ��Z���`�����^���ȏ�Ƃ������̂��A��X���ǂ̂悤�Ɉʒu�Â��Ă����悢�̂�����N�����B
�@ ���K�a�́A�u���������v���u�ƕ������Ƃ����R���e�N�X�g�ɂ����鏗�������v�ł͂Ȃ��������Ƃ������ӎ����q�ׂ���ŁA�ȉ��̂悤�Ɋe���\�҂Ɏ��₵���B�����q�̔��\�́A�c�@���q�����f���ɂ����ǍȌ�������サ�������w�Z���A�t���I�ɍ��Ƃ̗��z�I�ȏ����������E����悤�Ȑl�ނ�y�o�����Ƃ������ɋ����[���_�l�ł������B�t�͊w�Z�𑲋Ƃ������̒��ɂ����鍷�قɂ��ďڂ����������ق����B���p�P�̗��_�͔��Ɏa�V���傫�Șg�g�݂������̂ł��������A������`��������`�̃A���`�e�[�[�Ƃ��Ē��Ă����B������������`��_���邳���ɏ�ɏ����͔r������A�s��������Ă����̂��B�V��m���̔��\�́A�����I�ƈ�ʂɌ����Ă���l�`���p��t�F�A���[�E�e�C�����A�����|�p�Ƃ���̓I�ɑn�������Ƃ��ėL���ȃW�������ł��������Ƃ�������̂ł������B������������Ƃ��������������邱�Ƃ��ʂ����čK���ȃt�F�A���[�E�e�C���ƂȂ肤��̂��B��玟姃�ɑ��ẮA�u�������v���y������X���͂ǂ̂悤�Ɍ�����̂����₪�������B
�@
��l�̃R�����g�������A�e���\�҂���ȉ��̂悤�ȉ������������B�����q�́A�ߋ��̏�������ւ̃o�b�V���O�������悤�ɁA��������ɂ͍��Ƃւ̕��]�Ɠ����ɏ�ɂ�������̎��R�ƈ�E�������ɗ^������̂ł������B�܂��A����ɂ����鏗�̕��f�Ƃ������͎c����̂́A�t�͊w�Z�Ɍ����Ă݂�A�S�����Ƌ���ł��������߂ɁA�o�ϊi���ƊK���ɂ�鍷�ق��z���邱�Ƃ��\�ɂ��Ă����Ɖ��������B���p�P����́A1920�A30�N��ɂ����ẮA������`�҂Ə�����`�҂͋������čl�@����Ă������A�Ȍ�Z�N�V���A���e�B���Ɋւ��Ēj��������̌������ᔻ�����������Ƃ���A���҂̔F���̘g�g�݂͑傫���O�����̂ƂȂ����Ɛ������������B�܂��A�A�т̉\���͎c���Ă����ׂ����Ƃ͂����A�j���̐��ɏ��̐������ݍ��܂�Ă��܂��_�ɂ��Ă̊댯����F�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��q�ׂ��B�V��m���́A�l�`�Ƃ����W���������̂��ƕ������̂��ƂŃo�C�A�X�̂��������`�Ŕz�u����Ă��邱�Ƃ���{����`�I�X���Ɋׂ肪���ł��邱�Ƃ�F�߂Ȃ�����A���鑤���K�͂���R�ꂱ�ڂꂽ�����������ɑ����Ȃ������邩���d�v�ł���Ǝ咣�����B��玟姃��1920�A30�N��̏����Ԃ̓������Ƃ́A���������i�ِ��j���̕Ԃ����Ƃ��ĕ\�ۂ���Ă����Ƃ����_�ŁA��Ɏ���������A���ʂɈʒu�Â����Ă����Əq�ׂ��B���̌�A�t���A�[������R�����g�������悹���A�����ȓ��_���s��ꂽ�B���̃Z�b�V�������̂��̂����ꂩ��̏��������̂���Ȃ锭�W��\����������̂ł������B
 |
�Z�b�V����3�eTrans�|�f�̉\��
�ҁF�O�H�֎q�i�����̐����q��w��w�@���m����ے��ACOE�������j�@
�y���\�ҁE�^�C�g���z
�������i������w�j
�@�u�؍��j�������w����x����\�ؗ��Ɓw�e�����x�̌o�ϊw�\�v
���������i�����Y�p��w�j
�@�u��ˁw�j���������鏗���x���߂���F���_�̃|���e�B�N�X�\�g�����X����W�F���_�[�E�N���G�C�e�B�u�ց\�v
�^�W�����E���i���ԏ��q��w��w�@�@�C�m�ے��j
�@�u�ݓ����N�l�ꐢ�̏������w�|��x����\�h�L�������^���[�ɂ������w�I��I�Y�p�x�𒆐S�Ɂ\�v
��������i�����̐����q��w��w�@���m����ے��ACOE�������j
�@�u�w�����x�̕��ꂩ��w���x�̕���ց\������b�q�w�e�x�ɂ݂�N�B�A�Ƃ��Ă̕\�ہ^�\�ۂƂ��ẴN�B�A�\�v
�y�R�����e�[�^�[�z
���p���i���ԏ��q��w�j
�勴�m��i������w�j
�y�i�@��z�˒J�z�q�i�����̐����q��w�j
�y���@�l�z�g�p����͓��{��E�؍���B�Q���� 169���B
�ʐ^�͂�����
�y�T�@�v�z
�@
�{�Z�b�V�����̃^�C�g���u�eTrans-�f�̉\���v�́eTrans-�f�Ƃ́A��n�飂Ƃ����Ӗ��������A���������ĕ����ƃW�F���_�[�Ɋւ�邢�����̋��E�������čs��������ƁA�����ɐ����鉽�炩�́i�s�j�\�����A�{�Z�b�V�����̃e�[�}�ł���B
�@
�܂��������́A2003�N�ɓ��{�ŋN�������u�~�\�i�V���h���[���v�ɒ[����ؗ��u�[���ɏœ_�āA���{�̒����N�������؍��j���X�^�[�ɕ�������̏��i�����u�e�����̌o�ϊw�v�Ɩ��Â��Ď��̂悤�ɘ_�����B�؍��j���̃C���[�W�́A���{�̍��x�ȕ����Y�ƂƍI�݂Ɍ��т��ď����A�����Ə�̗̈悪�}���ɏ��Ɖ����ꂽ�B���̌��ʁA�����̂ƂȂ������{�̒����N�����Ɋ؍��j���ɑ���ڋ߉\�Ȉِ����I�e�����������o�������B���̂��Ƃ́A���{��`�\���̒��ł̃W�F���_�[�̕s���艻�ݏo���\���������Ă���B���������{�ɂ���Ă��̑��݂��K�肳���؍��̒j���X�^�[�́A��I�W���\�Ƃ���u�C���[�W�v��u���i�v�ł���A����͑��l�ȃW�F���_�[�W�̑z���͂̌͊����ے����錻�ۂł�����B
�@
�����Ē����������A�u��ˁv�ɂ����Ēj����������������ۂɐ���������̃W�F���_�[�g�g�̕s���艻�������A�W�F���_�[���̃v���Z�X�̍čl��ʂ��Ă��̘g�g�݂̕ϊv�̉\����T�����B�j���͐����̐��𗣒E����䂦�̉������^���邪�A�����̐��̋��E���̖��Ӗ����������炷���̂ł͂Ȃ��B�������j���������鏗���́A�����w�I���ق̎��_�����a���������A����������邱�Ƃɂ���Ă̂ݔF���\�ƂȂ�B�܂��ɂ��̓_�ɁA���̓���O��Ƃ���u�g�����X�v����A�W�F���_�[���Ɏ���֗^����u�W�F���_�[��N���G�C�e�B�u�v�ւ̓]���̉\��������A���ꉻ�s�\�Ȃ��̂�c���\�Ȃ��̂ɂ���Ƃ����A�W�F���_�[�E�|���e�B�N�X�̉\�������邱�Ƃ��ł���Ǝ咣�����B
�@
�^�W�����E���́A���{�Ő��삳�ꂽ2�̃h�L�������^���[�w�C���̃���������x�i�T�N���f��ЁA2004�j�ƁwHARUKO�x�i�t�W�e���r�A2004�j�ɕ`�����ݓ����N�l�ꐢ�̏����������グ�āA�A���n��`�A�ƕ������A���������̒��Ŕޏ������̐����Ӑ}�I�ɖY�p������ꂽ���Ƃ𖾂炩�ɂ��A���̐��𑨂��������߂́u�|��v�̕K�v�������������B�u�ݓ��v��r��������{���O�̍��ʍ\���̓����ł́A�A���n��`�Ɖƕ����������d���āA���Ƃ��Ɂu��v�̋]���I�Ȗ�������������A�u���ՓI�ȕ�v�Ƃ��Ă̐��݂̂������������B���̂��ߔޏ������́u��v�ȊO�́u���j�v�͏W�c�̋L������폜����Ă��܂����A�x�z����ɂ���ĕs���Ɍ������^�B������邱�������ޏ������̐������������j���ł���̂́A�ޏ������́u���Ȍ���v�́u�|��v��ʂ��Ă݂̂ł���Ǝw�E�����B
�@
�Ō�ɕ�������́A������b�q�̏����w�e�x�i1972�j�ɕ`�����u�����v�ƌ���ł���u���v�����f���邱�Ƃɂ��A���̍�i�̃N�B�A��]�����݂��B�܂��u�����v�����镃���̋ߐe���Ɍ����鐫�ʓ@�̓��ʉ��ƁA���̉ߏ�ȕ\�ۂ䂦�ɐ����靘���̉\��������B����ɂ��́u�����v�̕�������u�����v�́u���v�̒��قɂ�錋���ƁA�u���v������Ƃ��Ă̊O�ݐ������������Ă��̎�̐�������s�\�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��Ă���_�ɒ��ڂ��āA���̌��������ʓ@�K�͂ɗ��ł����ꂽ����̌n�ւ̒�R�ɂق��Ȃ�Ȃ����ƁA�����ēǎ҂̂����鐫�̎�̂̑�������e����䂦�ɁA�������́u���v���N�B�A�Ȃ��̂̕\�ۂ��\�ɂ��Ă���Ƃ̉��߂��������B
�@
�ȏ�4���̕��ċ��p�ʂ��A�u�g�����X�v�Ƃ͈ړ��̗��ꂪ�ω��̋Ȑ��Ƃ��ċL�������̂ł���ƒ�`���������ŁA���̂悤�ɃR�����g�����B�z���ɂ���Đ����鋰��Ɩ��͂Ƃ������`������������A������ς���\���́A�|��ɒʂ�����̂ł���B�ݓ��ꐢ�ł����e�̐����A��e�C�f�I���M�[�ɑ�����ꂸ�ɕ\���ł���u�|��v�̌���Ƃ͂��̂悤�ȉ\�������������̂łȂ���Ȃ炸�A����́A�u������ǂ݁v��u���������v�ȂǂƂ������ނ̂��̂ł���B���������g�̓I�ȁu����v�͏�ƌ��т����߂ɁA�ؗ����˂Ō�����悤�ȁA��̓I�ȕω��̗l����悷��\����������ł���B���̂��Ƃ͂܂��A���������\�����t�@���^�W�[���L���Ă��邱�Ƃ��Ӗ����A���̓_�ŁA�t�@���^�W�[�̓N���G�C�e�B�u�ɓ���������̂ł���B�܂��w�e�x�ɂ��ẮA�Ō�ɒ��ق��Ă���u���v�Ƃ�����̂��A���ɂǂ̂悤�Ȍ�����ĕό`���Ă����\���������Ă��邩�����ƂȂ��Ă��邾�낤�B
�@
�����đ勴�m�ꂪ���̂悤�ɃR�����g�����B�{�[�_�[��g�����X�̖�肩�猩���y�E�����W�������ۂ̉��߂́A��O�I�Ȃ��̂���\�������܂��Ƃ�����˂ɂ��Ẳ��߂Ƌ��ʂ�����̂ł���A�ǂ�����A�{�[�_�[���z����Ɖ������������������������Ă���Ƃ������ۂƂ��đ����邱�Ƃ��ł���B�����A�{�[�_�[���z���邱�Ƃɂ���Ă���ɑ����̂��̂��r������c�߂��Ă����̂��A�ݓ����N�l�́u��e�v�̕���^���j�ł���B�ݓ����N�l�̕�e�̋��Ɋ��������Ƃ������]�����̃R�����g�́A���̋��ɓ��{�l�j�������S���Ă��邱�Ƃɖ��ڒ��ł��邪�䂦�ɁA��e�C�f�I���M�[�̕|�����ؖ��������̂ƌ����A��|��ɂ͎������̂Ɠ�����̂Ƃ̃o�����X���d�v�ł��邱�Ƃ��m�F������B�܂��A�w�e�x�Ɍ�����u�j�E�v�̃C���[�W�́A�������E�����邱�Ƃւ̊�т��������̂ł���A����́u�������v��u���N�l�v�������t�����Ă��镉�̃C���[�W�ƊW���āA���{�Љ�̕����I�Í��ʂ�\�ۂ������̂Ɖ��߂ł���B
�@
�ȏ�̃R�����g�ɑ��A�҂͎��̂悤�ɓ������B�����́A�������������Ă���t�@���^�W�[�����̂܂�e��������u�|��v���Ă������ƂŁA�Ȃ�炩�̉\�����L�����Ă������낤�Ƃ̌����������A���́A�ؗ��Ɍ����鏗���Ə���̖��́A���̕����I�����I�W�ɂƂ��čm��I���ʂƔے�I���ʂ����邱�Ƃ��ēx�w�E�����B�^�́A�u�|��v�Ƃ͑z���̖͂��ɂ��邱�Ƃ��������A�����́A���ʓ@�I�ȃA�C�f���e�B�e�B�E�|���e�B�N�X����̂���ǂݕ�����̖|��Ƃ��Ē������Ƃ��Ċm�F���A�܂��u�j�E�v�ɂ��Ă̍ĕ��͂����݂����Ƃ̈ӌ����������B
�@
���O���玿�^���鎞�Ԃ��Ȃ������_�͎c�O���������̂́A�u�g�����X�v�������đ��l�ȕ�������̉\�������ꂽ�{�Z�b�V�����́A�R�����e�[�^�[�̑勴�̌������A�����Y�Ƃ���j�Ɋւ�����̂�����{�ƒ��N�����̊W�ɂ����镉�̕����ɂ܂Ńe�[�}���y�сA�{�[�_�[���z���邱�Ƃ̈Ӗ��Ɖ\������ɂ͕��̑��ʂɂ��Ă��l������������̂ł������B
 |
�Z�b�V�����S�@�푈�����ƃW�F���_�[
�ҁF�����]�Îq�i�����̐����q��w��w�@���m����ے��ACOE�������j�@
�y���\�ҁE�^�C�g���z
�|���a�q�i�����̐����q��w�j
�@�u�X�N���[������̎莆�͂ǂ��ɓ͂��̂��\�\���ؕĂ̐푈�f��ƃW�F���_�[�����v
���f���i�؍��|�p�����w�Z�j
�@�u�푈�Ə����\�\�w�Ō�̏ؐl�x�v
������i�����̐����q��w��w�@���m����ے��ACOE�������j
�@�u����i�ɂ�����A���n��`�Ə��������̖��\�\�A���n�ւ̈ړ��҂Ɓw�|�W�x�̕\�ۂ𒆐S�Ɂv
�������i���ԏ��q��w��w�@�@���m�ے��j
�@�u�푈�Ǝ��v
�y�R�����e�[�^�[�z
���X�z��i������w�j
�������i���ԏ��q��w�A�W�A�����w�Z���^�[���j
�y�i�@��z�����T�q�i�Óc�m��w�j
�y���@�l�z�g�p����͓��{��E�؍���B�Q���� 116���B
�ʐ^�͂�����
�y�T�@�v�z
�@
�V���|�W�E��2���ڂɂ́A�u�푈�����ƃW�F���_�[�v�Ƒ肵�āA�����T�q�i��̂��ƁA4���̔��\�҂�2���̃R�����e�[�^�[���}���A��4�Z�b�V�������s��ꂽ�B
�@
�܂��A��ꔭ�\�ҁA�|���a�q�́u�X�N���[������̎莆�͂ǂ��ɓ͂��̂��\���ؕĂ̐푈�f��ƃW�F���_�[�����v�Ƒ肵�A�ߔN��p�����ɐ��삳�ꂽ���ؕĂ̐푈�f����A�u�����v�̐��x�I�E�S�I�\���Ƃ̊W�ŁA�Ƃ��ɃZ�N�V���A���e�B�ɂ܂��푈�Ɨ~�]���ǂ̂悤�ɔz������Ă��邩�����ɁA���͂����B�ꌩ���Ĕ����W�Ԃ��Ă��邩�Ɍ�����f��ɍ���Ă���z���\�[�V�����e�B���A�u���ɐ��r�v�Ƃ��Đ펀�̊�������^���Ă���A�z���G���e�B�V�Y���𗬗p���ے肷�邱�̌������u�́u�،��v���A�ǂ̂悤�Ɂi�s�j�\�ȕ\�ۂɂȂ肤�邩���l�@�����B
�@
���ɁA���f������푈�Ə����\�w�Ō�̏ؐl�x��Ƒ肵�A�����w�Ō�̏ؐl�x�i���\���]���A1974�j�ƁA���̖|�Ă̓����̉f��i1979�j�̕��͂�ʂ��āA���N�푈�Ƃ��������Ԑ푈�������ɏ������e�����������l�@�����B70�N�㏉���Ɏ����ݒ肵�����̍�i�́A20�N�̍Ό���k��A���N�푈�����������̕����ɂ���������̏W�c�E�l�ƁA�₳�ꂽ�ނ̖��ɑ��钇�ԓ��ł̏W�c�����\�ޏ��͢�Ԉ��w��ƌĂ�A�p���I�ɂ��̖�����������ꂽ�\�������Ă���A���͂����Ƀt���C�g�́w�g�[�e���ƃ^�u�[�x�ɂ����颕��E����Ƣ�ߐe����̘A���Ƃ��̋֊��̕�������A���̢�������c��ƌĂ��j�������Ԃ̐킢�̒��ŁA�������e�㓯���Ƃ݂Ȃ��ꂸ���\�͂̑ΏۂƂȂ邳�܂�_�����B
�@
�u����i�ɂ������A���n��`�����������̖��\�A���n�ւ̈ړ��҂Ɓu�|�W�v�̕\�ۂ𒆐S�Ɂv�\��������т́A�鍑��`�ɔᔻ�I�ȗ���ō�i�������A����������������u�V�������v�^�����Ƃ����Ėڟ����A���͒鍑���͂̓����ɑ������j���m���l�̈���o���A��x�z���ւ̊S�⏗�ɑ��闝���������Ă���Ƃ��āA�ނ̓��ɐ��ޖ��ӎ��̐A���n��`�Ə���������\�����B����ɁA�����u�M�w�l�v�Ɓu�|�ҁv�Ƃ��ē������ǂ͓��ꎋ���r�������i���̒j���o��l���̎����ɁA�A���n���u�ȁv��u�|�W�v�Ƃ��ĕ\�ۂ��������鍑�̐A���n��`�̐헪�����Ԃ点�A���̏����\�ۂɁA�A���n��`�Ə��������̋��ƊW�������邱�Ƃ��w�E�����B
�@
�u�푈�Ǝ��v�\�������h���I�N�́A�푈�Ƃ���ɂ�鎀�����̊ϓ_���猩�������݂�W�J�����B�j�����S�I�����\���ɂ����āA�푈�Ɋւ���ӎv���肩��r�����ꂽ�����A�펞�ɗ^�����鐫�����͉����A�܂��펞�̐��\�͂����ɂ����Ȃ�Ӗ��������A�����ɏ��̈ꐶ�ɉe�����y�ڂ����Ƃ��������A�푈�ɔ������̗l�X�ȑ��ʂƂƂ��ɍl�@�����B�푈�����v�ƍl���鐭�{�ɑ��āA�푈�Ƃ���ɂ�鎀���A�l�̐l���ɂ�����r���Ɣj��̒��_�Ƃ��đ����邱�ƂŁA�푈�̔j�Ɩ��v����_�����B
�@
�����̔��\�ɑ��āA���X�z��͌܂̖���N������`�ŃR�����g���s�����B���ɁA�u�����\�ۂ̐����w�v�Ɩ��ł{��ɂ����āA�����\�ۂݏo������ҁi��́j�A���ݏo���ꂽ�\�ہi��i�j�A���̕\�ۂ��Љ�I�ɗ��ʂ��钆�ʼnʂ����������I�E���j�I�Ȗ����i��e�j�Ƃ����O�҂��A���m�ɕ������ĕ��͂���K�v������Ǝw�E�����B
�@
���ɁA�{�Z�b�V�����̈����u�푈�v�\�ۂ̏ꍇ�A����ȍ~�́u�푈�v�̗��j�I�Ӗ��ƁA���̐푈�́u�\�ہv�Ƃ̊W���A�ᔻ�I�Ɏ�舵����K�v���q�ׂ��B
�@
��O�ɁA���N�푈�̕\�ۂ��w�g�[�e���ƃ^�u�[�x�̋t�]���ۂƑ��������ɑ��āA�ނ���t���C�g���Ӗ��Â����l�ԎЉ�̒����̂�������̂��A�������A���̕����g�g�݂��A��O�̋L�������邽�߂ɁA�t�]���ꂽ�u���C�v�̕\�ۂƂ��āA����ɂ������o�Ȃ܂܌���Ă���Ƃ������������Ă����B�����Ă����������c�_�ɈÂɊ܂܂��O��\�����̎Љ�𢐳�C��Ƃ݂Ȃ��A��X�̌������u���C�v�̑��ɂ���Ƃ����v�����݁\�ɂ́A��Ɏ��Ȕᔻ�I���_�����K�v�����������B
�@
��O�ɁA�|���_�̢�s�\��Ƣ�\��̑����ɂ��葱���颏،����^���ɎƂ߁A�^�����鏬�X�́A����Ȃ����N�Ƃ��āA�@�I�쉺�ɂ����X���@�𒈒݂�ɂ��ꂽ�푈�\�͂̑����̐l�Ԃ̊��ւ̑z���͂��������邩�Ɖ�X�̂������₤���B
�@
�Ō�ɁA���X���g�̐��ł�������̕\�ە��͂ɂ��āA���̏����\�ۂ̒��ŁA���X������������̐A���n�x�z��鍑��`�̂�������������Ă���ƍl����ӏ����A����т͟��Ζ{�l��ᔻ���镶���ɓ]�����ėp���Ă��邱�Ƃ��w�E���A�h�ӂ�\����ƂƂ��ɁA�ތ^�����ꂽ�C�f�I���M�[�I�����̍Đ��Y�ɉ��S����뜜��\�������B
�@
�����čs��ꂽ�������̃R�����g�ł́A�푈�̎�͍̂��Ƃł���A�푈���ł��鍑�ƂɂȂ邽�߂̉ߒ�������ߑ�̗��j�ł��������Ƃ��m�F�����B���̂悤�ȍ��Ƃ��`�������̂͌R�l�ł���j����̂ł���A�푈�������j�ɑ�������̂Ƃ��Č����̂ɑ��A�ی���e��ɂ���s���Ƃ��Ă̏��́A�ƒ�E��E�������ƌ��т�����Ƃ��āA�푈�����ɂ�����@�I�ȑΏ̍\�}�̑��݂𖾂炩�ɂ����B��L��4���\���Ҍ�������̓@�I�\�}�̒��ŋc�_����Ă��邱�Ƃ���A���̍\�}����E���ċc�_���邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂��Ƃ����₢�����B
�@
���҂̃R�����g�ɑ��A�܂��|���́A���X�̑��̎w�E�ɓ��ӂ��A�܂��A���̎w�E�����@�̍\�}������͂�E���ׂ��Ƃ��ł���ɂ�������炸�A�����̌ÓT�I�ȍ\�}�𗘗p�����f�悪��ʐ��Y����Ă��鎖���ւ̋������{���\�Ɏ��炵�߂��Əq�ׂ��B�܂��A���X�̑�O�̎w�E���āA�t���C�g�̋ߑ㎩��`���ɂ��Ă̗��_���A�\�́E���ʁE�ߑ㍑�ƂƂ̊W�̒��ŁA��茻��ɑ������`�̎�̌`���Ƃ��ĉ��߂ė��_���������K�v������Əq�ׂ��B����ɁA�Â������X�����L���Ă�������݂̂悢�u����v���g���Ȃ���A���V���ɏ�̐������i�߂��Ă��鎖�ԂɌx����炵���B
�@
���́A�t���C�g���_�́A�����̏W�c�̒��ŁA�������E�������A���������̓����ɂ���Ȃ���r�������̈��̃A�i���W�[�Ƃ��ėp�����Ƃ��āA���X�ɉ��������B
�@
����т́A�w����l���x�̓����̂悤�ȏ���鍑����̑�O���f�B�A�i�V���j�ɕ`���������A�l�I�����ł͏��������������Ă��邱�Ƃ��A�{���\�̌_�@���Ɛ��������B
�@
���h���I�N�́A�푈���Ƒ��⍑�ւ̈��䂦�ɍs�����Ƃɔᔻ�������K�v�ƁA�l�̔߂��݂⎩�R�̔j��̊ϓ_������푈���l�������K�v���J��Ԃ����B
�@
�����̉����ɑ��āA�ēx���X���A���Ɋւ��āA��Ƃƍ�i�̕����̕K�v������A���X���g�́A���Ƃ͕ʂ̊ϓ_����A������̌�����薾�炩�ɏ���������A���n��`����Ă������i���A���{�̐푈�ւ̕��݂�j�ސ헪�Ƃ��ėp���Ă���Əq�ׂ��B�����āA�|���̏�̐����̔����ɂ��āA�ɂ߂ē�������p���A����Ȏ��{�����ƂƂ��ɁA���ꉻ���ꂽ�C���[�W�̑���ɂ���Đ����w���s���錻�݁A���Ԃ������������Ɉق������邱�Ƃ̂ł����X�\�ےm���l�̖������ɂ߂ďd�v�ɂȂ邱�Ƃ��w�E���A�ꓯ���ە������B
�@
�Ō�ɁA�|�����@�̍\�}�̉�̂Ƃ��āA���B�Z�p����ł����_���̘g�g�݂��ϗe���ׂ��������Ă���ƕ⑫������A���̎���ɗ��h���I�N���Z���������A���݉}�̉ۑ�ł���푈�����ƃW�F���_�[�ɂ��Ă̖{�Z�b�V�����͖�������B
 |
�Z�b�V����5
���E���h�e�[�u���@
�ҁF�R���ؕ�q�i�����̐����q��w��w�@���m����ے��ACOE�������j
�y�i�@��z�|���a�q�i�����̐����q��w�j
�y�R�����e�[�^�[�z�������i���ԏ��q��w�j
�y���@�l�z�g�p����͓��{��E�؍���B�Q���� 116���B
�ʐ^�͂�����
�y�T�@�v�z
�@
���E���h�e�[�u���́A�����̐����q��w�W�F���_�[�����Z���^�[�����ڂ�����̃R�����g����J�n���ꂽ�B�ڂ͂��̂悤�ȕ����\�ۂ̌����̈�ɂ����Ă��A�Ȋw�E�e�N�m���W�[�̊ϓ_�A�Ƃ��ɁA�푈�ƃe�N�m���W�[�̖�����舵���悤��Ă����B�����āA�R�����e�[�^�[�̋��������A���؏����V���|�W�E���̊�旧�ĎҁE�Q���҂̎��_����A����̃V���|�W�E������т���ɐ旧���j�c�A�[�̈Ӌ`�A�����č���̓W�]�ɂ��ĕ�I�ɃR�����g�����B���͂܂��A���̓��̏��������҂ɂ�鋤���v���W�F�N�g�̊��J�ÁE�Q���̖ړI�ɂ��Đ��������B���ɂ��A���̌����҂����́A�\�ۂ̖��\�\�Љ�I�ȗ��Q�E�Č��̖��\�\�𗝉������ŁA���ꂼ��̗��ꐫ����E������������ɂ���B�Ƃ�킯�A���j�𗝉�����ۂɁA���҂����ꂼ��̗��ꐫ���đ��݂ɗ��������Ԃ������Ă��邩�͋^�킵���B���̋^�₪�A��c�ɐ旧���ė��j�c�A�[���܂߂�Ƃ����A���̃v���W�F�N�g���J�n�����_�@�ł���B�ߔN�A���ؗ����̑��ݗ��������߂�~���̍��܂��w�i�Ƃ��āA���̂悤�ȃV���|�W�E�����p�ɂɊJ�Â���Ă��邱�Ƃ͊m�������A�𗬂̌p���͍���ł���A���Ǒ��H�ɓ˂������邱�Ƃ������B�������A�݂��������ɓ����ߑ�̍Č��������A�������ƁA�����Ă���炪�����Ȃ���j�I�E�����I�E�����I�ȗ͂ɂ���č\�z���ꂽ�̂����L���邱�Ƃɂ���āA�V���ȓ����͍����Ȃ���𗬂��邱�Ƃ͉\���Ǝv����B���ꂪ���̃v���W�F�N�g�̖ړI�ł���B
�@
����ɋ��́A���̌����҂��݂��̗��ꐫ���āA�]���̗��j�\�ۗ����ɑ���ᔻ�I�Ȏ������l�������ŁA�݂��Ɏ��ӓI�ȂЂƂтƂ̘b���A�V���Ȍ��t�E�\�ۂ����o�����Ƃ��d�v�ł���Ǝw�E�����B����ɂ��̍ہA����ꂪ�ߑ�̎Y���Ƃ��Ă̔F���̘g���ɂ��邱�Ƃ��\�S�Ɏ��o���A�������̂���K�v������A�������ƊςɊ�Â��\�ۑ̌n���A�C���^�[�^�g�����X�A�W�A�̋�Ԃőa�ʉ\�ȕ\�ۂƂ��č��ς���w�͂��K�v���Əq�ׂ��B�����āA�V���|�W�E���ł̂��ꂼ��̔��\�́A�����̓_�܂�����ŏ����\�ۂ��ĉ��߂��A�V���ȋ�Ԃ�T���w�͂������ƌ��Ȃ���邾�낤�ƁA���̃v���W�F�N�g�����ăR�����g���I�����B
�@
�����āA�t���A����̎��^�����ֈڂ����B���₨��щ����͑���ɘj�������A�_�_�͈ȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B�܂��A���ꉻ�╨��̉��߁A���߂��鋤���̂ɒ�R���邽�߂ɁA�����Ȃ���@���l�����邩���߂����āA�\�ە��͂̊w�p�I�Ȓ~�ς�ᔻ����肢���������ʂ����邱�Ƃ�A�ΈēI�ȕ\�ۂ����o�����Ƃ���Ă��ꂽ�B�܂��A����Ɋ֘A���āA�{�����G�Ȃ��̂��A���f�B�A�ɂ���Ĕ��ɒP��������\�ۂ���Ă��錻���A�}�C�m���e�B�ɂ��}�W�����e�B�ւ̒�R�̍���q�ׂ�ꂽ�B����ɑ��A�m���l�͂����C�Â������łȂ��A�N�e�B�r�X�g�ł���K�v�����邾�낤�A�Ƃ����w�E��A��R����Ƃ����s�ׂ͍���ł͂�����̂́A��R���邱�ƂŊ����̃V�X�e����h�邪�����̂��Y�܂��Ɠ����ɁA���ꂪ�V���Ȑ����I�������Ґ������J�n�n�_�ł��邱�Ƃ����ɂ߁A�c�_����K�v������A�Ƃ̉������Ȃ��ꂽ�B�Ō�Ɏi��̒|���a�q�́A�W�F���_�[�Ґ��Ƃ������j�I�Ɏ��Ԃ������ĕ��G�ɐ�������Ă����V�X�e���̕ϊv�ɂ͈�����̎��Ԃ��K�v�ł��邱�Ƃ܂��A�ނ����Ȃ��Ƃ́A�������Đ�]�������������邱�Ƃł���A�ϊv�Ɍ����Đi��ł���Ƃ����m�M�������Ƃ��Əq�ׁA�܂��u������ǂށv�n�_�ŗ����~�܂��Ďv�l���邱�Ƃ��K�v�Ƃ̒Ń��E���h�e�[�u���͏I�������B����A�����^�̈�����l�X�Ȍ����҂��������݂A�{�v���W�F�N�g���p���E���W���Ă�����]������������[�������V���|�W�E���ł������B
 |
�Ǔ��E�ӎ�
�@�{�N�̓��؏�����c��1�����قnj��10��3���ɁA��1�Z�b�V�����ŃR�����e�[�^�[�����ĉ���������K�݂ǂ肳��̓ˑR�̂������̔ߕ�ɂӂ�A�����ƈ����݂ɂ����܂���B���̉�c�ɂ͑�1��ڂ���i���̂���ɂ͌������\�҂Ƃ��āj���Q��������A�܂��{21���ICOE�v���O�����̎�X�̎��݂����x�����ĉ�����A���̂ǗL�Ӌ`�Ȃ��ӌ��݂̂Ȃ炸�A�W�F���_�[�������i�ւ̔M���v����`���Ă��������܂����B
�@��K�݂ǂ肳��ɁA���炽�߂Ă킽�������̊��ӂ̋C�����������ƂƂ��ɁA���̎u���p���ׂ��A���ꂩ�����w�w�͂��ĎQ��܂��B
�����̐����q��w21���ICOE�u�W�F���_�[�����̃t�����e�B�A�v
�v���W�F�N�gD�u���_�\�z�ƕ����\�ہv����ѓ��؏�����c�̒S�������E�w���ꓯ
�i�v���W�F�N�gD�E���؏�����c��\�@�|�� �a�q�j
|