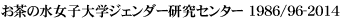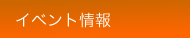ハイディ・ゴットフリード
ウェイン州立大学准教授赴任期間:2007年1月-2007年3月
第22回IGS夜間セミナー
ジェンダー・労働・政治 Gender, Work and Politics
期間
2007年1月25日(木)、2月2日(金)、8日(木)、15日(木)
担当
ハイディ・ゴットフリード Heidi Gottfried (ウェイン州立大学准教授、お茶の水女子大学ジェンダー研究センター外国人客員教授)
内容

最初の講義では、広義にとらえた労働に関するフェミニスト研究を検討する。家父長制と資本主義を含むマクロ構造、ミクロレベルの社会的相互依存、そしてマクロとミクロの中間にあたる労働市場の制度や組織構成や組織慣行について議論する。その上で、ジェンダー研究の手法と対象がアプローチによって異なることを明らかにする。例えば労働市場論では、固定的な職業上の分業と賃金の不平等を個人もしくは制度的特徴によるひとつの機能であると見なす。そしてこの分業や不平等は女性または雇用主の意思決定と関連していると捉える。一方、分析のレベルと対象を変えた場合、社会的・文化的に重要となる問題とその要素、また組織内および組織的実践に応じたジェンダーの差異化のパターンに着目する分析も存在する。このことは労働に関するフェミニスト研究の多様性を示唆していると言えよう。
第2回目の講義では、ジェンダー、労働、政治に関するフェミニスト理論の領域を狭め、労働市場における女性の選択や機会に影響を及ぼす公共政策について検討する。本講義では、フェミニストによる政策や国家間の比較研究分析で用いられる分析手法を概観する。これらの分析手法は政策や政治上の国家および地域間の相違を分類するに留まらず、女性労働の実態が国によって多様である原因を分析するための研究でも利用されている。
第3回と4回目の講義では、現実の労働問題を取り上げながら前回までの2回の講義で述べた制度学派フェミニスト理論の応用を試みる。第3回目の講義では労働と雇用政策におけるジェンダー・バイアスを明らかにするための方法として、ジェンダー化「様式」の多様性について講義する。第4回目の講義では、増加傾向にある女性の非正規雇用(パートタイムなど)を明らかにした上で、ジェンダーの(不)平等に対する政策インプリケーションを提示する。まず、日米間の政策を比較して政策の類似点と相違点を明らかにする。そして最後に本セミナーの締めくくりとして、労働におけるジェンダーの公正を達成するために必要な政策や規制の枠組みを構築するためのフェミニスト理論を検討する
回 |
日時 |
テーマ |
司会 |
コメンテータ |
1 |
1/25(木) |
イントロダクション:労働のフェミニスト理論 先行研究をもとに労働のフェミニスト理論が提起している諸問題(権力構造、企業組織、政治・社会制度)を考察する。 |
伊藤るり |
足立眞理子 |
2 |
2/2(金) |
政策、政治と労働:比較研究およびトランスナショナルな研究方法 雇用政策および法律・政治制度の比較研究を検討し、様々な研究アプローチや具体的な分析手法を紹介する |
足立眞理子 |
堀内光子 |
3 |
2/8(木) |
労働・雇用関連施策とジェンダー(不)平等 労働基準に関する法律および雇用関連施策の形成過程が女性の雇用に及ぼす影響を検討する。 |
足立眞理子 |
伊藤るり |
4 |
2/15(木) |
経済的自立の確保へ:ジェンダーと非正規雇用に関する日米比較研究 日本における女性の雇用パターンを事例とし、非正規雇用の増加が雇用者の経済的自立を妨げていることを明らかにし、労働とジェンダーに関する新たな枠組みを構築する方向性を探る。 |
足立眞理子 |
大沢真理 |
第1回 1月25日(木)18:30-20:45
イントロダクション:労働のフェミニスト理論
18世紀の後半Mary Wollstonecraft の女性の権利の弁護以降、フェミニストは女性に対する固有で不平等な処遇を非難してきた。生産と再生産の相互関係に関する共通認識が生まれたことで分断したフェミニズムは再び統合することとなり、こうしてジェンダーに関する諸問題に対する合意が形成された。その一方、男性が享受している特権や女性が被っている不利益が改善しない原因とそのメカニズムについては、現代のフェミニストの間で論争が続いている。第1回目の講義では労働のフェミニスト理論が提起している諸問題を検討する。
参考文献
Acker, Joan. (2006). “Introduction: The Feminist Problem with Class,” in Class Questions Feminist Answers, Lanham: Rowan and Littlefield, p.1-13.
-------. (2006). “Feminists Theorizing Class-Issues and Arguments,” in Class Questions Feminist Answer, Lanham: Rowan and Littlefield, p.15-44.
Recommended reading:
Gottfried, Heidi. (2006). “Feminist Theories of Work,” in Marek Korczynski, Randy Hodson, Paul Edwards (eds.), Social Theory at Work. Oxford: Oxford University Press, p.121-54.
第2回 2月2日(金)18:30-20:45
政策、政治と労働:比較研究及びトランスナショナルな研究方法
1980年代以降、女性労働者に「優しい」労働環境をつくるための新しく多様な政策(例えば雇用機会、育児休業、労働時間とジェンダー関係の調整)が実施されるようになった。しかしながら、労働市場において不利益を被っているのは依然として女性であり、雇用のパターンは男女間、国家間で大きく異なっている。本講義では、雇用政策、政治さらに国家に関する比較研究やトランスナショナルな研究を概観する。先行研究を検討することによって、フェミニストの多様なアプローチの長所や短所を評価することができる。また政策形成のダイナミックスや決定要因、それらが男性と女性に及ぼす影響なども考察することができるものと考えられる。これらの分析手法は労働政策と雇用における変化に関する研究でしばしば用いられ、第3回と4回目の講義で詳しく取り上げる予定である。
参考文献
Woodward, Alison. (2004). “European Gender Mainstreaming: Promises and Pitfalls of Transformative Policy,” in Heidi Gottfried and Laura Reese (eds.), Equity in the Workplace: Gendering Workplace Policy Analysis. Lanham: Lexington Books, p.77-100.
Haas, Linda (2004). “Parental Leave and Gender Equality: What Can the United States Learn from the European Union?” in Heidi Gottfried and Laura Reese (eds.), Equity in the Workplace: Gendering Workplace Policy Analysis. Lanham: Lexington Books, p.183-214.
第3回 2月8日(木)18:30-20:45
労働・雇用関連施策とジェンダー(不)平等
フェミニスト研究者はジェンダーに関する不平等を作り出している様々な「力」に関する理解を深めるために、ジェンダーに敏感な視点で政策形成過程や福祉国家の発展を分析したり、労働組織の転換に関する理論及び事例研究を行うなど極めて重要な研究に取り組んできた。これら二つの側面は、労働と社会保障の統合を可能にする「知的融合」のために必要であると認識されている。しかしながら、従来フェミニストによる政治研究が労働に関する規制を研究対象としてこなかったという背景から、先行研究では労働と社会保障に関する方法論上の区別を融合させるには至っていない。本講義では労働規制に関する研究を取り上げ、方法論上の分類を超えた研究手法について検討する。労働規制に関する研究を検討することは従来の理論構築を発展させるというよりも、むしろジェンダー化されている規制の形態、意図された(または意図されていない)影響を理解することを目的とする。女性の労働とキャリアに関連した政策の枠組みが、どのように明確(または不明確に)女性の労働力参加の集約度を助長、もしくは制限しているのだろうか?規制におけるジェンダー諸問題を考察することによって、フェミニスト政治研究は今日の労働(雇用) 形態を批判的に捉え、労働規制という言葉に潜んでいるジェンダー化された規範を再検討することができるものと考えられる。最終回の講義では労働時間に関する政策や労働時間の調整(パート労働やアルバイト)をテーマとし、性別役割分業のバランスをはかりながら労働におけるジェンダー平等の達成を可能にするような政策を提言したい。
参考文献
Walby, Sylvia. (forthcoming). “Theorizing the Gendering of the Knowledge Economy: Comparative Approaches,” in Sylvia Walby, Heidi Gottfried, Karin Gottschall, Mari Osawa (eds.) Gendering the Knowledge Economy: Comparative Perspectives. Palgrave, p.3-50.
Gottfried, Heidi. (forthcoming). “Changing the Subject: Labor Regulations and Gender (In)Equality,” in Ilse Lenz, Charlotte Ullrich, Barbara Fersch (eds.), Gender Orders Unbound: Globalization, Restructuring, Reciprocity. Leske + Budrich, p.1-32.
第4回 2月15日(木)18:30-20:45
経済的自立の確保へ:ジェンダーと非正規雇用に関する日米比較研究
パート労働などの非正規雇用が雇用全体に占める割合は高く、この傾向は特に、女性労働者において顕著に見られるパターンである。この状況は契約上の権利、リスク、責任に関わる規定の含みが質的に転換していることの現れである。実証的なトレンドを議論した上で特定の国の発展を検討することで、複雑化している非正規雇用の特質とジェンダー化された特徴を明らかにすることができる。実際に、正規雇用においてジェンダー化している特質を検討することは、非正規雇用の実態を理解し、この雇用形態がどの程度ジェンダー化されているのかを分析するための手がかりとなる。これらの雇用パターンは日本の雇用制度の柱となっている制度的構造の設計と密接なつながりがあるものと思われる。女性の非正規雇用が高い比率である事実は日本の雇用制度に根付いているジェンダー・バイアスとして部分的に説明できるものと考えられる。さらに、非正規雇用の増加に伴って、経済的な「保障」は失われていくこともあわせて指摘したい。本講義の後半では、労働とジェンダー規制の枠組みにおけるパラダイムシフトが必要であるとの視点から、経済的なセーフティーネットの構築に向けた新しい方向性を提示するつもりである。
参考文献
Osawa, Mari. (forthcoming). “Comparative Livelihood Security Systems from a Gender Perspective, with a Focus on Japan,” in Sylvia Walby, Heidi Gottfried, Karin Gottschall, Mari Osawa (eds.) Gendering the Knowledge Economy: Comparative Perspectives. Palgrave, p.201-245.
Standing, Guy. (2006). “Economic Insecurity and Labour Casualisation?threat or promise?” Keynote Address, Pathways to Economic Security, University of Northern British Columbia.
Gottfried, Heidi, Steve Rose, Heidi Hartmann and David Fasenfest. (2004). “Autonomy and Insecurity: The Status of Women Workers in the United States,” Bulletin of the Society for the Study of Working Women, 46:17-39.
女性と労働に関するウェブサイト
カナダにおけるジェンダーと非正規雇用
www.genderwork.ca
労働と政治
www.iwpr.org