IGS通信2010
- 3/ 7 新任のアカデミック・アシスタントとして、平野恵子さんが着任しました。
- 1/ 31 杉橋やよい特別講義「ジェンダー統計について」
- 1/28 IGS研究会「政治思想とフェミニズム理論の乖離と接近」
- 1/13 山本由美子特別講義「国連開発計画とジェンダー主流化」
- 1/ 8 シンポジウム「ケア・エコノミーの現在」
- 12/ 1 新任の研究推進支援員として、板井広明さんが着任しました。
- 11/17 佐藤梢さん、鍋野友哉さん送別会
- 11/13 エヴァ・キテイ教授講演会「ケアの倫理からグローバルな正義論へ」
新任のアカデミック・アシスタントとして、平野恵子さんが着任しました。
3/7 新任のアカデミック・アシスタントとして、平野恵子さんが着任しました。 以下は自己紹介です。 |
「この度アカデミック・アシスタントとして着任いたしました平野恵子です。 2011/4/5掲載 |
杉橋やよい特別講義「ジェンダー統計について」
|
2011/2/4掲載
|
IGS研究会「政治思想とフェミニズム理論の乖離と接近」
|
1/28(月)、同志社大学大学院教授岡野八代氏を講師に迎え、研究会「政治思想とフェミニズム理論の乖離と接近」が開催された。近刊予定である博士論文を元にした岡野氏の報告は、リベラリズム理論の中心にある公私二元論が、実は社会的排除や不平等を算出するという矛盾を内包している点を批判し、これまで政治思想や理論の中心から疎外されてきた「家族」や「依存」、「ケアの倫理」というテーマに焦点をあて、フェミニズムの議論から社会を構想するという試みであった。既存の政治思想が自立した成人男性をモデルとした社会制度を構想し「依存」私的領域に属するものとして議論から排除してきたのに対し、岡野氏は、乳幼児のように生存の為には誰かに依存しなければならない存在を前提とする社会を構想し、「依存」への対応を母子間等の関係性に留めおかずに集合的責任として認識するという思考の転換を提案する。さらには、こうした思考の転換が、近代的な主権国家を超えた新しい共同性の産出に向かうものであるとも示唆している。 2011/5/11掲載
|
|
山本由美子特別講義「国連開発計画とジェンダー主流化」
|
1/13(木)、バンコクの国連開発計画(UNDP)アジア太平洋地域事務所でプログラムスペシャリストとして活躍する山本由美子氏による特別講義が開催された。受講生は、本年度のアジア工科大学との研究交流プログラム「タイで、開発とジェンダーを学ぼう」に参加する学生を中心とした博士前期課程開発・ジェンダー論コース院生。講義内容は、国連組織およびUNDP事業の概略説明、講師自身がアジア太平洋地域事務所で担当している業務の内容や、現在の職に就いた経緯など。開発支援の現場ではどのような考え方のもとに事業が進められているかという、最先端の報告と合わせて、大学院修了後のジェンダー領域の専門家としてのキャリアパスを考えるうえでも参考になることの多い講義であった。後半の質疑応答では、院生たちそれぞれの研究テーマに関する質問が出され、AIT研修を事前に控え、個々の研究内容についての考えを深める機会ともなった。 2011/2/23掲載
|
|
シンポジウム「ケア・エコノミーの現在」
|
ジュリー・ネルソン氏による基調講演では、2000年に発表された共著論文「For Love or Money -- Or Both?」を基に、以降10年間の動きを追っての議論が展開された。 2011/2/4掲載
|
|
新任の研究推進支援員として、板井広明さんが着任しました。
12/1、新任の研究推進支援員として、板井広明さんが着任しました。 以下は自己紹介です。 |
「イギリスの18~19世紀の功利主義哲学、とくにJ.ベンサムの研究をしています。ジェンダー研究については、ほとんど素人なものの、ベンサムの女性論を論文にしたこともあり、少なからぬ関心を抱いてきました。研究支援推進支援員の仕事として、ジェンダー研究センターの催しに関わることになるので、ジェンダー研究を知るとてもよい機会をいただいています。 2010/12/22掲載 |
佐藤梢さん、鍋野友哉さん送別会
11/17(水)昼食時、佐藤梢さん(科研費研究員、10月末退職)、鍋野友哉さん(研究支援推進員、11月末退職)の送別会が開かれました。 |
|
センター教員をはじめ、スタッフ、院生ともども、お二人にはいろいろな場面で大変お世話になりました。手際の良い仕事ぶりでセンター活動を支えてくださった佐藤さん、鍋野さんに改めてお礼を申し上げるとともに、お二人の今後ますますのご活躍をお祈りいたします。 2010/12/3掲載 |
エヴァ・キテイ教授講演会「ケアの倫理からグローバルな正義論へ」
|
エヴァ・キテイ氏の講演は、著書『愛の労働あるいは依存とケアの正義論』(牟田・岡野監訳、2010 白澤社刊)に基づき、さらにグローバルな視野を交えて展開された。キテイ氏は、依存者および依存労働者を含むすべての人が平等であるような平等概念およびそのための条件を模索し、「依存」が人間にとって不可避の条件であり、依存とそのケアが入れ子状になった状態であることを認識するなら、平等な社会とは公正でケアに満ちた社会でなければならないと述べた。そして依存者だけでなく彼女たちをケアする依存労働者のニーズに社会はどう応えるべきか、という重要な視座を提起した。本講演では、このような「関係性にもとづく平等」の議論に加え、移民として依存労働を提供する女性たちとグローバルな経済的不平等の問題について考察すべき局面であることも指摘した。コメンテーターである江原由美子氏は、依存者のケアが「ライフ選択」の問題には還元しえないにもかかわらず、このことは男女平等の主張の中で見えなくなってしまったこと、日本では依存労働者の立場の弱さにはあまり触れられてこなかったことなどを指摘し、これらの点において、依存と依存労働を軸にしたキテイ氏の議論が、極めて示唆的であると述べた。 2010/11/29掲載
|
|

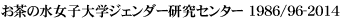

 1/31(月)、金沢大学の杉橋やよい准教授によるジェンダー統計についての特別講義が開催された。受講生は、本年度のアジア工科大学との研究交流プログラム「タイで、開発とジェンダーを学ぼう」に参加する学生を中心とした博士前期課程開発・ジェンダー論コース院生。講義は、ジェンダー統計の基礎から統計データの扱い方の基本、GIIやGGGIなど現在の国内外のジェンダー統計動向にまで話が及ぶ、包括的な内容であった。
1/31(月)、金沢大学の杉橋やよい准教授によるジェンダー統計についての特別講義が開催された。受講生は、本年度のアジア工科大学との研究交流プログラム「タイで、開発とジェンダーを学ぼう」に参加する学生を中心とした博士前期課程開発・ジェンダー論コース院生。講義は、ジェンダー統計の基礎から統計データの扱い方の基本、GIIやGGGIなど現在の国内外のジェンダー統計動向にまで話が及ぶ、包括的な内容であった。 世界の主流と比べて遅れを見せており、2010年12月に決定した第3次男女共同参画基本計画においてようやくジェンダー統計の整備が必要であることがうたわれた。また、内閣府男女共同参画局と統計機関の連携は弱く、ジェンダー統計の整備・活用に向けて克服すべき課題は多い。
世界の主流と比べて遅れを見せており、2010年12月に決定した第3次男女共同参画基本計画においてようやくジェンダー統計の整備が必要であることがうたわれた。また、内閣府男女共同参画局と統計機関の連携は弱く、ジェンダー統計の整備・活用に向けて克服すべき課題は多い。













