IGS通信2012
- 1/14 国際シンポジウム「災害、復興におけるジェンダー公平性を問う」
- 12/12 「災害、復興とジェンダー公平な国際共生社会の構築」プロジェクト 第2回研究会
- 7/23 「災害、復興とジェンダー公平な国際共生社会の構築」プロジェクト 第1回公開研究会
- 7/18 ジェンダー研究センター研究交流会
- 5/29 公開シンポジウム「原発とサステイナビリティ・サイエンス―ジェンダー視点からの課題を考える」
国際シンポジウム「災害、復興におけるジェンダー公平性を問う」
本年度の「災害・復興とジェンダー公平な国際共生社会の構築」プロジェクトの締めくくりとして、タイ・インドネシア・日本の災害、復興への事例を実践者、研究者より報告し、ジェンダー公平な国際共生社会の構築にむけて議論する国際シンポジウム「災害、復興におけるジェンダー公平性を問う」が開催されました。当日は、交通機関が麻痺するほどの大雪という悪天候となりましたが、大勢の方が会場に足を運んでくださり、質疑応答・討論の時間には熱い議論が交わされる、実り多い集まりとなりました。また、サイドイベントとして、東日本大震災被災地の女性が撮影した写真と撮影者の言葉からなる「フォト・ボイス」展示も開催されました。シンポジウムでの議論の概要は以下の通りです。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *パリチャート・クロンカント氏は、台風被害の多いタイ南部の農村を事例として、警報が発令された際に老年者がいつ、どのように避難意思決定をするのかの詳細な聞き取り調査をもとに、地域の規範が老年者の避難行動の重要な決定要因となることを明らかにした。調査地域の老年者による「誰かに頼るのは恥である」「ほかの人を邪魔してはいけない」といった意識は、「他人に迷惑をかけない」ことが老年者自身の尊厳につながることを明示している。したがって家屋が耐えられないといった緊急を要する状況でなければ、隣人の避難、家族の者による促し、村長からの指令などの公的な誘導なしに、進んで避難行動をとることはないのである。 アラビヤニ・アブバカル氏は、2004年12月に発生したスマトラ島沖大地震・インド洋津波被害からの復興のために、バンダ・アチェ市に設置された機関(以下、復興庁)で、「女性、子供、福祉、ジェンダー」課長として復興事業に携わった。その経験から、復興庁の事業の焦点がどこに置かれたか、またその予算配分について、ジェンダー主流化の観点から分析をおこなった。復興政策において、ジェンダー関連施策は、「『アチェ・ニアスをより良くする』という復興事業の目的達成を後押しする」ものとして重要視され、女性男性(配偶者、兄弟姉妹)双方に土地所有権を保証する「土地共同名義プログラム」の実施などにより、地域社会のジェンダー平等が推し進められた。 平野恵子氏は、スハルト政権崩壊以降進展する地方分権化とジェンダー主流化が、災害復興・対策とどのように関連しているのかについて、インドネシア・アチェ州を事例に政策、予算分析をおこなった。結果、最も多い予算配分を受けているのは、「インフラ開発向上とその最適化」「教育の質と保健サービス」という二つの項目であった。教育の質・保健サービスプロジェクトには、女性、子ども、エンパワーメントといったキーワードが付加されており、災害対策と民主化の証左として進展する地方分権化、そしてジェンダー主流化との関連性が明らかにされた。 池田恵子氏の報告は、2012年9月におこなったアチェ調査に加え、東日本大震災女性支援ネットワーク研修担当として被災地にて実施した調査をもとに、日本の災害復興への政策的インプリケーションを提示している。東北の被災地においては、復興計画に発言できないなど復興の議論に女性が参加出来ない、女性や子どもへの暴力の増加がみられる、女性の労働負担(家庭責任)が増えるなど、ジェンダー視点に基づいた、避難と避難生活の課題が指摘された。アチェの事例から何を学べるかという点については、性別ごとのニーズ調査や世帯単位でのニーズ把握などの、情報の処理・共有方法の制度化、脆弱性のジェンダー分析といった、アチェの復興を後押ししたジェンダー主流化の取り組みの導入が挙げられた。 上記4名の報告を受けて、コメンテーターの足立眞理子氏は、多様なニーズが多様な時期に必要とされていることを、各報告が改めて明らかにしており、これは、災害に対するジェンダー分析を深めるものであると指摘した。続く質疑応答のセッションでは、セクシュアル・マイノリティへの支援や、日本の災害対策への提言などに関する質問が出され、タイ、インドネシア、日本の経験から、ジェンダー公平な社会の構築についての議論が展開された。 《開催詳細》 2013/5/24掲載
|
|
「災害、復興とジェンダー公平な国際共生社会の構築」プロジェクト 第2回研究会
| 「災害・復興におけるジェンダー公平な国際共生社会の構築プロジェクト」の第2回研究会が、12月12日に開かれました。2部構成の前半は、プレ研究会として、DVD『放射性廃棄物-終わらない悪夢』を視聴しました。後半は、ジュヌヴィエーヴ・フジ・ジョンソン著『核廃棄物と熟議民主主義—倫理的政策分析の可能性』の読書会で、5月29日に開催された公開シンポジウム「原発とサステイナビリティ・サイエンス―ジェンダー視点からの課題を考える」と7月23日の第1回公開研究会での議論に引き続き、「原発とジェンダー」の課題についての検討が行われました。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * アルテ独仏共同TV局が2009年に制作したDVD『放射性廃棄物-終わらない悪夢』は、国境を越える放射性廃棄物処理の実態をロシア、フランスやドイツなどでの取材をもとに明らかにした。増え続ける放射性廃棄物と激しさを増す反対派運動の現実を背景に、原子力エネルギ−産業で主導的な立場にあるフランスの関係者の様々な意見も紹介している。DVD視聴後、参加者は、放射性廃棄物処理の現実に驚くとともに、廃棄物問題は、「現代に生きる我々の能力を超えることを先送り」にし、「未来を抵当にした」ものであるという、DVD製作者からの問題提起に共感を示した。また、リプロダクティブ・ヘルス・ライツを核としながら、環境破壊に反対するエコロジカル・フェミニズムにも関心が寄せられた。環境汚染・破壊の問題を生殖や健康の側面からだけではなくて、正義論・倫理論からも議論する必要があるのではないかと、「熟議民主主義」への関連も指摘された。 続く読書会では、菅野琴客員研究員が報告した。まず、著者の言う「熟議民主主義」は、「すべての人(あるいはその代表者)にしかるべき情報を与え、強制を伴わない自由な参加により、継続的に討議や対話を続け、そこで得られた合意に基づいて政策への勧告や提言を行なうプロセスをさす」と、その定義を紹介。さらに、熟議民主主義は、実証主義の限界を超え、功利主義や現代義務論の短所を倫理的アプローチで補うことにより、核廃棄物管理のように、不確実で極度なリスクを伴う、高度に複雑な技術的、社会的、倫理的諸問題を含む、将来世代にも関わる問題領域での政策決定に有効であると論じている。そしてカナダでの核廃棄物管理機構の国民協議のプロセスを、熟議民主主義の諸原則を実現している取り組みとして取り上げ精査する。最後に、主導的陣営にいる人間の強い意思と実行力が、熟議民主主義の過程を左右することを、重要な教訓としてあげている。 報告発表後の討論では、熟議民主主義にジェンダーの視点を入れる必要性とその課題、生態系のレベルまで含み、より踏み込んだ将来世代論や、男性の性と生殖の健康と権利論を明確にする重要性が語られた。さらに、男性性としてジェンダー化された権力としての核保有(原子力エネルギーを含む)と安全保障のあり方や、戦後日本社会の功利主義的傾向などが、日本での原発問題を熟議民主主義で考察し、政策遂行する場合の課題として取り上げられた。 |
|
《開催詳細》
プレ研究会 ――――――――――――――――――――――― 第2回研究会 ―――――――――――――――――――――― |
2013/5/24掲載 |
「災害、復興とジェンダー公平な国際共生社会の構築」プロジェクト 第1回公開研究会
本研究会では、5月29日の公開シンポジウム「原発とサステイナビリティ・サイエンス―ジェンダー視点からの課題を考える」で課題となったサステイナビリティ概念について、法政大学サステイナビリティ研究教育機構長である舩橋晴俊氏にご教示いただきました。要旨は以下の通りです。 舩橋氏の分析に対し、これはジェンダー研究の課題とも共通する重要な論点であるとの応答がなされ、サステイナブルな国際社会を形成するための研究課題が再確認された。舩橋氏が示したサステイナビリティの含意と議論によって「ジェンダー配慮の経済社会循環システム」という研究視座が明確になり、本プロジェクト研究にとって非常に示唆的な研究会となった。 2013/5/24掲載
|
ジェンダー研究センター研究交流会
7月18日、研究協力員として東京に滞在中のユン・ジソ氏(カンザス大学政治学部講師)を迎え、研究交流会(英語)を開催しました。比較政治学的観点から米国と韓国のジャーナリズムを分析し、政策形成過程における政府と市民社会の相互作用を考察した報告で、ニューヨーク・タイムズ紙とハンギョレ新聞の一面記事と政策形成参与度の相関分析を示しつつ、韓国の報道は官僚や大統領に集中し、米国は政府機関全般への偏重を明らかにされました。報告に対し菊池啓一氏(ピッツバーグ大学大学院政治学研究科Ph. D候補生)は、民主主義を構成する重要な要件であるにもかかわらず比較政治学的な研究蓄積がほとんど無い「報道の自由」と政治コミュニケーションの関係を扱ったものとしてユン氏の報告を高く評価し、調査対象の2008年以外について検討する必要性と、「記者クラブ」による政府の報道統制の問題を提起しました。続いて大木直子氏(お茶の水女子大学リサーチフェロー)は、日本でもマニフェスト政治が主流になって以来首相など政治家に関する報道が肥大し、政策決定過程に多大な影響を与えているとし、政府と報道機関構成員のジェンダー不均衡と、女性政治家へのジェンダー・ステレオタイプな報道の問題を投げかけました。今回の研究交流会では、本学院生、研究協力員など、若手研究者を中心に活発な議論が行われました。 2012/8/8掲載
|
|
公開シンポジウム「原発とサステイナビリティ・サイエンス―ジェンダー視点からの課題を考える」
2012年度の「国際社会ジェンダー論」(ジェンダー研究センター提供の大学院博士前期課程科目)公開シンポジウムは、日本と国際社会が共有する緊急課題として、「世界における『フクシマ』」をテーマとして取り上げました。福島原発事故の経験を事例に、国連が提唱してきた「持続可能な開発」の文脈を踏まえ、ジェンダーの視座から課題を考察することを目的としています。
2013/5/24掲載
|
|

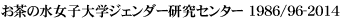













 舩橋氏は、サステイナビリティを、各時点での「人間社会の生産・消費活動が、それらの諸条件を破壊せず、それによって人間社会が永続的に存続可能であること」と定義づけている。ここから導き出されるサステイナビリティには、永続的なものと期限付きのものがありうるが、永続的なサステイナビリティのためには、1)社会と自然環境システムの間の循環、2)循環の維持、3)生物種の多様性の維持、4)蓄積(環境負財と資本蓄積)、5)多様な角度からの技術の選択、6)環境制御システム論の視点、の6つの条件が満たされる必要があるとし、これらの条件を詳細に検討すると、現在の原子力開発は、決してサステイナビリティの域に到達するものではないと断言した。続けて、サステイナブルな社会への移行を妨げるメカニズムとして、人間の持つ「賢明さ」を実現する規則的原則、「公平(衡平)」、発言権・決定権の分配における「公正」、そして「人権擁護」のs4点にわたる「欠如」を挙げ、原子力開発の課題は、この4つの価値理念(公正、公平、人権、賢明さ)の実現とサステイナビリティとの連関の問題であると指摘した。
舩橋氏は、サステイナビリティを、各時点での「人間社会の生産・消費活動が、それらの諸条件を破壊せず、それによって人間社会が永続的に存続可能であること」と定義づけている。ここから導き出されるサステイナビリティには、永続的なものと期限付きのものがありうるが、永続的なサステイナビリティのためには、1)社会と自然環境システムの間の循環、2)循環の維持、3)生物種の多様性の維持、4)蓄積(環境負財と資本蓄積)、5)多様な角度からの技術の選択、6)環境制御システム論の視点、の6つの条件が満たされる必要があるとし、これらの条件を詳細に検討すると、現在の原子力開発は、決してサステイナビリティの域に到達するものではないと断言した。続けて、サステイナブルな社会への移行を妨げるメカニズムとして、人間の持つ「賢明さ」を実現する規則的原則、「公平(衡平)」、発言権・決定権の分配における「公正」、そして「人権擁護」のs4点にわたる「欠如」を挙げ、原子力開発の課題は、この4つの価値理念(公正、公平、人権、賢明さ)の実現とサステイナビリティとの連関の問題であると指摘した。


 舘かおる
舘かおる
 菅野琴
菅野琴




 会場風景
会場風景