IGS通信2011
ジェンダー研究センター 研究報告会
 3月6日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室にて、2011年度ジェンダー研究センター研究報告会が開催されました。研究報告会はIGS研究協力員による研究成果および計画の発表を柱とし、議論をたたかわせることで、今後の研究展開に資するとともにセンター教員、関係者そして研究協力員間の交流を推進することをねらいとしています。 3月6日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室にて、2011年度ジェンダー研究センター研究報告会が開催されました。研究報告会はIGS研究協力員による研究成果および計画の発表を柱とし、議論をたたかわせることで、今後の研究展開に資するとともにセンター教員、関係者そして研究協力員間の交流を推進することをねらいとしています。
高橋さきの(本学・東京農工大学非常勤講師)は、「テクノバイオポリティクスという視角」と題する報告を行い、科学技術論の分野におけるジェンダーの課題として、労働法制、技術と「男らしさ」創出の関連性などについて論じました。次に根村直美(日本大学教授)が、「生成としてのサイボーグに関する一考察」と題して報告し、ティラドー、ドゥルーズ、ガタリの議論に依拠して、既存の社会関係を再構築しうる〈サイボーグ〉としての自己と身体の理論化を試みました。最後に崔京実(中国共産党中央編訳局)が、中国共産党中央編訳局のおもな内容を紹介し、職場での経験を交えつつ、中国の人口政策(一人っ子政策)について解説を行いました。鋭い問題提起とともに建設的な意見が提出され、充実した報告会となりました。
《開催詳細》
【日時】2012年3月6日(火)17:00-21:00
【会場】お茶の水女子大学 学生センター棟4階 第5会議室
【タイトル】ジェンダー研究センター2011年度研究報告会
【報告者】高橋さきの(IGS研究協力員、東京農工大学非常勤講師)、根村直美(IGS研究協力員、日本大学教授)、崔京実(IGS研究協力員、中国共産党中央編訳局)
【司会】徐阿貴(IGS研究機関研究員)
【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
【参加者数】7名
|
|
このページのトップにもどる
AITワークショップ「災害とジェンダー」
2012年2月29日、本年度のAITワークショッププログラムの総まとめとなる、公開ワークショップ「災害とジェンダー」が開催されました。朝から雪となる悪天候でしたが、学内外から多くの方に足をお運びいただき、大変充実した内容のワークショップとなりました。
例年のAITワークショップでは、本学院生のタイAITへの派遣とAIT院生の本学への受入という、交換研修プログラムを実施しています。しかし、本年度は、AITが2011年秋のタイ大洪水で被災し、未だ機能の復旧が完全でないことから、本学にAIT教員と院生を招聘しての特別プログラムとなりました。履修生は、「災害とジェンダー」という題目に沿った自らの研究テーマを決め、4回の事前勉強会(勉強会招聘講師については下記参照)や調査研修を通して各々の研究スキルを磨き、公開ワークショップの場での研究発表に至るまでの一連の研究プロセスを実習しました。また、本企画のコーディネーターは、博士後期課程ジェンダー学際研究専攻院生が担当しています。
 公開ワークショップは、本学教員・舘かおるとAIT教員・日下部京子による、本学とAITの大学間学術交流協定やAITワークショップについての説明を含む挨拶から開始しました。これに続く、フィリップ・ドニー、日下部京子のAIT教員2名からの、タイ・ラオスにおける「災害とジェンダー」事例報告は、災害発生時のジェンダー課題についての基本的な問題を再確認する内容でした。履修院生による報告では、高田千尋が東日本大震災の被災地支援における企業の活動を取り上げ、スタンナード・ポリーは被災地のセクシャル・マイノリティ支援に目を向けるなど、先端的な課題に焦点が当てられています。AIT院生サムディ・タン、佐々木忍のタイ大洪水に関する報告は、入手の難しい細かいデータをまとめての分析となりました。加えて、被災地の女性支援に取り組むみやぎジョネットの八幡悦子氏からは、被災体験や被災地状況、避難所の現実、支援活動状況などを含む、被災地のジェンダー課題についての生の声が届けられました。コメンテーターの池田恵子氏からは、個々の報告についての丁寧なコメントと合わせて、院生達の今後の研究の展開を期待する激励の言葉が贈られました。 公開ワークショップは、本学教員・舘かおるとAIT教員・日下部京子による、本学とAITの大学間学術交流協定やAITワークショップについての説明を含む挨拶から開始しました。これに続く、フィリップ・ドニー、日下部京子のAIT教員2名からの、タイ・ラオスにおける「災害とジェンダー」事例報告は、災害発生時のジェンダー課題についての基本的な問題を再確認する内容でした。履修院生による報告では、高田千尋が東日本大震災の被災地支援における企業の活動を取り上げ、スタンナード・ポリーは被災地のセクシャル・マイノリティ支援に目を向けるなど、先端的な課題に焦点が当てられています。AIT院生サムディ・タン、佐々木忍のタイ大洪水に関する報告は、入手の難しい細かいデータをまとめての分析となりました。加えて、被災地の女性支援に取り組むみやぎジョネットの八幡悦子氏からは、被災体験や被災地状況、避難所の現実、支援活動状況などを含む、被災地のジェンダー課題についての生の声が届けられました。コメンテーターの池田恵子氏からは、個々の報告についての丁寧なコメントと合わせて、院生達の今後の研究の展開を期待する激励の言葉が贈られました。
ワークショップ終了後に、本学履修生とコーディネーターが書いた感想文書がありますので、そちらもご参照ください。
履修生受講感想(PDF, 515KB)
コーディネーター感想(PDF, 500KB)
|
***************************************************************
《講師招聘勉強会詳細》
[第1回勉強会]
【日時】2012年1月10日(火)
【講師】鳫咲子(参議院事務局企画調整室調査員/早稲田大学非常勤講師)
【タイトル】「3.11大震災後の子どもの状況:東京における母子避難者支援」
【参加者数】10名
[第2回勉強会]
【日時】2012年1月23日(月)
【講師】池田恵子(静岡大学教授)
【タイトル】「『災害とジェンダー』研究の成り立ちと展開」
【参加者数】12名
[第4回勉強会]
【日時】2012年2月8日(水)
【講師】丹羽雅代(女性の安全と健康のための支援教育センター運営委員)
【タイトル】「災害をジェンダー多様性の視点から考える」
【参加者数】14名
2012/4/27掲載 |

鳫咲子

池田恵子

丹羽雅代
|
このページのトップにもどる
国際ワークショップ 東アジアにおける「女性と科学/技術」
 1月30日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室において、国際ワークショップ「東アジアにおける『女性と科学/技術』」が開催されました。本ワークショップは、2011年度IGS研究プロジェクト「『科学技術とジェンダー』に関わる研究の諸局面の検討」および、2010年度科学技術社会論・柿内賢信記念賞「アジアにおける女性研究者に関する科学社会論的研究」(受賞者:小川眞里子)の一環です。 1月30日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室において、国際ワークショップ「東アジアにおける『女性と科学/技術』」が開催されました。本ワークショップは、2011年度IGS研究プロジェクト「『科学技術とジェンダー』に関わる研究の諸局面の検討」および、2010年度科学技術社会論・柿内賢信記念賞「アジアにおける女性研究者に関する科学社会論的研究」(受賞者:小川眞里子)の一環です。
基調講演において、小川眞里子氏(三重大学/IGS客員教授)からは、ワークショップの歴史や、女性と科学/技術の研究状況が紹介されました。第1セッションでは、韓国からは、Eun-Kyoung LEE氏(Chonbuk National Univ)より、2000年代に始まった理工系女性サポートプログラムに関する報告がなされました。台湾からは2名が参加し、Yen-Wen PENG氏(National Sun Yat-sen Univ.)は、台湾とEUの状況を統計で比較しました。Li-Ling TSAI 氏(National Kaohsiung Normal Univ.)は、台湾の女性理工系研究者に対して行なったアンケート調査の報告をしてくださいました。第2セッションでは、日本から、財部香枝氏(中部大学)が男女共同参画学協会連絡会の大規模調査について、河野銀子氏(山形大学)が女子中学生の状況について、また、三浦有紀子氏(東京大学)がポジティブ・アクションについての報告を行ないました。アジアではEUのようにまとまった調査が行なわれていないことから、国ごとの比較が難しいことが指摘されましたが、こうした国際的な連携によってさらに調査・研究が進んでいくだろうことが実感できる、有意義なワークショップとなりました。
《開催詳細》
【日時】2012年1月30日(月)13:00~17:00
【会場】お茶の水女子大学 学生センター棟4階 第5会議室
【タイトル】「東アジアにおける『女性と科学/技術』」
【挨拶】舘かおる(お茶の水女子大学)
【基調講演】小川眞里子 (三重大学/IGS客員教授)‘History and Situation of East Asian Workshops for Women Researchers.’
【報告】≪第1セッション 韓国・台湾の報告≫
■Eun-Kyoung LEE (Chonbuk National Univ. Korea), ‘Past, Present, and Future of Women in S & T in Korea.’
■Yen-Wen PENG (National Sun Yat-sen Univ. Taiwan), ‘She Figures - Statistics and Indicators on Gender Equality in Science. EU vs. Taiwan.’
■Li-Ling TSAI (National Kaohsiung Normal Univ. Taiwan), ‘Survey outcome of women scientists’ family and career conditions in Taiwan.’
≪第2セッション 日本の報告≫
■財部香枝(中部大学)’ Large-Scale Survey of Japanese Scientists and Engineers.’
■河野銀子(山形大学)’Science for Junior-high School Girls in Japan.’
■三浦有紀子(東京大学)’Positive action in Japan.’
【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
【共催】2010年度科学技術社会論・柿内賢信記念賞(JSSTS Yoshinobu Kakiuchi Memorial Award)「アジアにおける女性研究者に関する科学社会論的研究」(受賞者:小川眞里子)
【参加者数】13名
|
|
このページのトップにもどる
シンポジウム「ケア・エコノミーの現在」
11月22日、イギリスからフェミニスト経済学者のスーザン・ヒメルヴァイト教授(Open University)をお招きしてシンポジウム「ケア・エコノミーの現在」を開催した。
足立眞理子センター長の挨拶に続いて、ヒメルヴァイト教授から「ケア―フェミニスト経済理論と政策課題―」と題した報告が行われました。
報告では、家庭内における育児や介護などの無償ケア労働が国内総生産(GDP)の計算に入っていないこと、近年は市場で購入できる有償ケア労働が増加傾向にあること、そして有償無償を問わずケア労働のほとんどが女性によって担われていることなどが確認されました。そのうえで、女性がケア責任を引き受けることを当然視する社会規範が存在すること、それによって女性の雇用機会が制限されている関係について指摘されました。また、最近はケア・サービスの市場化が進んでいる一方で有償ケア労働が一般に低賃金職種であることから、ケアの質やケアを提供する人材の技能確保が難しい側面についても言及されました。加えて、機械を利用する製造業に比べてケア労働が労働集約的な個人サービスであるために生産性の上昇に限界がある点について、ボーモルの「コスト病」を用いて説明されました。
ヒメルヴァイト教授の報告に続いて、コメンテーターの堀芳枝先生(恵泉女学園大学准教授)からは、ヒメルヴァイト教授が論文で使用するcaringとcare workの用語の違いおよびイギリスでケア労働に携わる外国人労働者の待遇および人権に関するコメントおよび質問がありました。同じくコメンテーターの伊藤誠先生(東京大学名誉教授)からは、ヒメルヴァイト教授が図示したケア・ダイアモンド(ケアを提供する家族、市場、政府/自治体、地域社会/非営利団体の4部門)に関するコメントのほか、ケアについて考える際に子どもと高齢者の間で差異はあるのか等の質問がありました。また、本学大学院生の落合絵美からは、無償労働を担った人々の老後の年金権に関する考え方やこのような人々に対して年金を保障する場合に女性のケア責任を強化しかねない側面についてコメントおよび質問が提起されました。そのほか、学外研究者や大学院生からもコメントおよび質問が多数寄せられ、終始活発な議論が展開されました。
《開催詳細》
【日時】2011年11月22日(火)13:30~16:30
【会場】お茶の水女子大学 学生センター棟4階 第5会議室
【タイトル】Care: Feminist Economic Theory and Policy Challenges
【講師】スーザン・ヒメルヴァイト(Open University, UK)
【司会】足立眞理子(お茶の水女子大学)
【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
【助成】野村財団
【参加者数】19名
2012/2/20掲載 |

スーザン・ヒメルヴァイト

司会、コメンテーター

会場風景
|
このページのトップにもどる
IGSセミナー「グローバル金融危機後のアジアとジェンダー」
2011年11月21日、お茶の水女子大学(本館135号室)において、スナンダ・セン教授(インド社会科学院)をお招きして、IGSセミナー「Asia and Gender after the Global Financial Crisis」(共催:法政大学サステイナビリティ研究教育機構)が開催されました。
スナンダ・セン教授は、1973年から2001年まで、インド・ジャワハラ・ネルー大学経済学部で教鞭をとられ、2001年の退官後も、インド内外の大学で研究活動を行っている経済学者です。専門・関心領域は、国際金融、国際経済学、フェミニスト経済学です。
講義は、フェミニスト経済学の概論から始まり、グローバリゼーション下における女性労働、インド経済の現代的課題など、多岐にわたり、参加者の興味・関心をさらに喚起させるものとなりました。当セミナーは学内向けとして開かれたものであり、参加者の多くは、本学大学院生でした。30年以上の長きにわたって、学生の指導にあたってこられたスナンダ・セン教授は、参加した本学大学院生の質問に対して、丁寧にお答え下さいました。
《開催詳細》
【日時】2011年11月21日(月)13:30~16:30
【会場】お茶の水女子大学本館カンファレンスルーム(135号室)
【タイトル】「グローバル金融危機後のアジアとジェンダー」
【講師】スナンダ・セン(Institute for Studies in Industrial Development)
【司会】足立眞理子(お茶の水女子大学)
【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
【共催】法政大学サステイナビリティ研究教育機構
【参加者数】15名
2012/2/10掲載 |

スナンダ・セン
|
このページのトップにもどる
スーザン・ヒメルヴァイト教授ワークショップ
11月17日、イギリスからフェミニスト経済学者のスーザン・ヒメルヴァイト教授(Open?University)をお招きして大学院生を対象としたワークショップが開催された。
ワークショップの前半は、ヒメルヴァイト教授による「フェミニスト経済学および経済政策のジェンダー・インパクト分析」と題した報告が行われました。報告では、主流派経済学においてこれまで考慮されてこなかったジェンダー視点を組み込んだ経済学がフェミニスト経済学であることを確認したうえで、市場経済(有償経済)は育児や介護、地域活動といった無償経済と相互依存関係にあること、女性は無償経済において多大な貢献をしているにもかかわらずその貢献が主流派の経済理論から抜け落ちていることなどが指摘され、無償経済を組み込んだ経済理論を構築することの重要性について説明されました。
これに続いて、ジェンダー不平等を解消するための手法のひとつであるジェンダー・インパクト分析の紹介が行われました。ヒメルヴァイト教授はイギリスにおける税制改革を事例にして、税制が男女によって異なる効果を与えうることが指摘されました。例えば、所得税の減税は一定水準以上の所得者に対する減税効果をもちますが、女性は一般に低所得層に集中しているために減税の恩恵を受けにくいこと、減税による税収不足によって育児や介護に関わる福祉サービスが削減された場合、家庭の女性が無償労働によってその穴埋めを期待されるために結果として女性の負担が増大することなどが説明されました。
ワークショップの後半は、参加者によるコメントや質問、そしてそれらに対するヒメルヴァイト教授からの応答が行われました。大学院生である参加者はそれぞれ研究課題を持ち、その学問分野や研究方法、調査対象などが多岐にわたることから、多様な視点から活発なコメントおよび質問が提起されて知的刺激に溢れたワークショップとなりました。
《開催詳細》
【日時】2011年11月17日(木)13:30~16:30
【会場】お茶の水女子大学本館カンファレンスルーム(135号室)
【タイトル】Feminist Economics and the Gender-Impact Analysis of Economic Policy
【講師】スーザン・ヒメルヴァイト(Open University, UK)
【司会】足立眞理子(お茶の水女子大学)
【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
【助成】野村財団
【参加者数】16名
2012/2/20掲載 |

スーザン・ヒメルヴァイト

会場風景
|
このページのトップにもどる
盛岡第三高校プレ大学講座「メディアからジェンダーを考える」
本センターの研究機関研究員・徐阿貴が、10月12日(水)に岩手県立盛岡第三高等学校の緑丘プレ大学講座において、「メディアからジェンダーを考える:韓流を中心に」というテーマの授業を行いました。これは、盛岡第三高等学校から本学への、ジェンダーの問題・課題・研究等の入門的な内容の授業をしてほしいとの依頼を受けての出張授業です。
授業内容は、メディアにあらわれる男と女のイメージを題材に、社会の中で期待されている男性と女性の役割や関係について考えていく、というものです。韓国のドラマも取り上げ、文化の違いによるジェンダーイメージの違いにも眼をむけてもらいました。高校生の皆さんにとっては、Kポップや韓ドラをきっかけに、メディアを批判的に考える機会になったようでした。
盛岡第三高等学校の緑丘プレ大学講座についてはこちらのサイトに詳しく紹介されています。
2011/11/29掲載 |

授業風景

徐 阿貴
|
このページのトップにもどる
国際シンポジウム「アジアにおけるグローバル化とジェンダーの現在」
|
|
7月9日、お茶の水女子大学講堂において、国際シンポジウム「アジアにおけるグローバル化とジェンダーの現在:マクロ経済と社会構築」(後援:外務省、内閣府男女共同参画局、JICA、他)が開催されました。
同シンポジウムでは、ダイアン・エルソン氏(エセックス大学)による基調講演のほか、第二部「マクロ経済とジェンダー」では、マリア・フローロ氏(アメリカン大学)と大沢真理氏(東京大学)による、環境問題や生活保障システムをめぐるジェンダー分析についての研究報告がありました。続く第三部では、「災害とジェンダー」をテーマに、マリナ・デュラーノ氏(マレーシア・サインズ大学)、池田恵子氏(静岡大学)、竹信三恵子氏(和光大学)より、バングラデシュや日本の東日本大震災の被災状況を踏まえた報告があり、アジアのジェンダー課題についての最新の知見を共有する有意義な場となりました。
また、このシンポジウムは、国連開発計画(UNDP)とお茶の水女子大学の共催による集中セミナー「ジェンダーとマクロ経済に関する能力構築」(7 月4~16日、於国立女性教育会館)の公開フォーラムでもありました。アジア各地からのセミナー受講生も聴衆として参加し、アジア域内の研究者・実務家同士の交流を深める機会ともなりました。
本シンポジウムの講演・報告の内容は、2012(平成24)年3月刊行の『ジェンダー研究』第15号に掲載の予定です。
《開催詳細》
【日時】2011年7月9日(土)10:00~17:00
【会場】お茶の水女子大学 徽音堂(講堂)
【タイトル】「アジアにおけるグローバル化とジェンダーの現在:マクロ経済と社会構築」
【プログラム】
《第一部:基調講演》
・ダイアン・エルソン(エセックス大学)「グローバリゼーション下の金融・生産・再生産」
《第二部:マクロ経済とジェンダー》
【報告】
・マリア・フローロ(アメリカン大学)「環境の危機と社会的再生産:連関を理解する」
・大沢真理(東京大学)「生活保障システムの比較ジェンダー分析が示すもの:その機能不全がグローバル不均衡を生む」
【ディスカッサント】足立眞理子(お茶の水女子大学)
《第三部:社会構築とジェンダー》
【報告】
・マリナ・デュラーノ(マレーシア・サインズ大学)「対アジアODAのジェンダーを探る」
・池田恵子(静岡大学)「災害リスク削減のジェンダー主流化:バングラデシュの事例から」
・竹信三恵子(和光大学)「日本の災害から見るジェンダー課題」
【挨拶】羽入佐和子(お茶の水女子大学・学長)、八木浩治(UNDP東京事務所・代表代行)、岡島敦子(内閣府男女共同参画局・局長)、西野恭子(JICA経済基盤開発部ジェンダー平等・貧困削減推進室・室長)、マリア・フローロ(GEM-IWG)、マリナ・デュラーノ(DAWN)
【司会】足立眞理子/舘かおる/申琪榮(お茶の水女子大学)
【主催】お茶の水女子大学、国連開発計画(UNDP)
【後援】外務省、内閣府男女共同参画局、独立行政法人国際協力機構(JICA)、国際フェミニスト経済学会(IAFFE)、新時代の女性による代替的開発グループ(DAWN)、ジェンダーとマクロ経済に関する国際ワーキンググループ(GEM-IWG)
【事務局】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
【参加者数】206名
2011/12/6掲載 |
このページのトップにもどる
UNDP集中セミナー「ジェンダーとマクロ経済に関する能力構築」
a.jpg) 7月4~16日、国連開発計画(UNDP)とお茶の水女子大学の共催による集中セミナー「ジェンダーとマクロ経済に関する能力構築」が埼玉県の国立女性教育会館において実施されました。 7月4~16日、国連開発計画(UNDP)とお茶の水女子大学の共催による集中セミナー「ジェンダーとマクロ経済に関する能力構築」が埼玉県の国立女性教育会館において実施されました。
日本政府出資の「UNDPパートナーシップ基金」の支援を受ける本セミナー事業は、政策実務者や研究者を対象に、ジェンダー視点に立った政策立案やプログラム策定の能力構築を目的としたものです。昨年はフィリピン・ミリアム大学で開催され、本年度は日本における初の開催となりました。
受講生は、アジア太平洋地域を中心とする各国からの130を超える応募者から選考された19カ国からのフェロー40名。連日の講義は、欧米、アジア太平洋地域各国および日本国内からの政策実務担当者や研究者が担当し、「ジェンダーとマクロ経済」に関する専門性の高い講義内容となりました。セミナーには本学院生も聴講生として参加し、フェロー達と共に、ジェンダー政策立案の最先端の知見を学びました。
本セミナーについては、UNDPアジア太平洋地域事務所発行のニュースレターに報
告記事が掲載されています。
http://www.snap-undp.org/elibrary/Publication.aspx?ID=550
2011/12/6掲載
|
|
このページのトップにもどる
戒能民江講演会「私のジェンダー法学研究」
 梅雨の晴れ間となった6/4(土)、本学名誉教授・客員教授である戒能民江氏の講演会が開催された。冒頭挨拶に立った生活社会科学研究会会長の杉田氏からは、戒能氏が、ハラスメント問題等への取り組み等を通して大学の法リテラシーを高める推進力となってきたこと、21世紀COE「ジェンダー研究のフロンティア」の拠点リーダーとして学内のジェンダー研究・教育基盤強化の成果を挙げたことなど、着任以来の大学への貢献の数々が紹介された。これに続く講演は、大学学部時代に関わった「こつなぎ事件」闘争支援や「女子学生の会」の活動に始まり、1980年代の英国家族法の研究、DVやセクシャル・ハラスメントなど女性に対する暴力に関する研究等、これまで戒能氏が取り組んできた研究・活動の内容に加え、最近訪問してきた、東日本大震災被災地における女性グループの支援活動の様子にまで話が及んだ。1960年代以降の様々なレベルにおけるジェンダーと法のありようを振り返る内容となった。質疑応答では、多くの学生たちから、各々が向き合うジェンダー課題に関する質問などが出されたが、講演中で語られた、「あきらめない意思を持ち続ける」「あなたたちを尊重している女性たちがいる」という戒能氏の言葉は、これから社会へ出る学生をはじめ、戒能氏の後進となる若手研究者にとっても、困難に立ち向かう際の拠り所となるであろう。 梅雨の晴れ間となった6/4(土)、本学名誉教授・客員教授である戒能民江氏の講演会が開催された。冒頭挨拶に立った生活社会科学研究会会長の杉田氏からは、戒能氏が、ハラスメント問題等への取り組み等を通して大学の法リテラシーを高める推進力となってきたこと、21世紀COE「ジェンダー研究のフロンティア」の拠点リーダーとして学内のジェンダー研究・教育基盤強化の成果を挙げたことなど、着任以来の大学への貢献の数々が紹介された。これに続く講演は、大学学部時代に関わった「こつなぎ事件」闘争支援や「女子学生の会」の活動に始まり、1980年代の英国家族法の研究、DVやセクシャル・ハラスメントなど女性に対する暴力に関する研究等、これまで戒能氏が取り組んできた研究・活動の内容に加え、最近訪問してきた、東日本大震災被災地における女性グループの支援活動の様子にまで話が及んだ。1960年代以降の様々なレベルにおけるジェンダーと法のありようを振り返る内容となった。質疑応答では、多くの学生たちから、各々が向き合うジェンダー課題に関する質問などが出されたが、講演中で語られた、「あきらめない意思を持ち続ける」「あなたたちを尊重している女性たちがいる」という戒能氏の言葉は、これから社会へ出る学生をはじめ、戒能氏の後進となる若手研究者にとっても、困難に立ち向かう際の拠り所となるであろう。
《開催詳細》
【日時】2011年6月4日(水)14:00~16:00
【会場】お茶の水女子大学共通講義棟1号館304号室
【タイトル】戒能民江先生ご講演「私のジェンダー法学研究」
【講師】戒能民江(お茶の水女子大学名誉教授)
【挨拶】杉田孝夫(お茶の水女子大学)
【司会】小谷眞男(お茶の水女子大学)
【主催】生活社会科学研究会、ジェンダー研究センター、花経会
【参加者数】116名
2011/6/8掲載 |
|
このページのトップにもどる
公開シンポジウム「危機における国連機関の役割と戦略的ジェンダーの視点」
紛争、自然災害等様々な種類の危機に直面している国際社会。その中で、国連がどのような役割を果たしているのか、また国連活動の現場ではジェンダーの視点がどのように生かされているのかをテーマとしたシンポジウムが5月18日に開催された。
女性と健康の分野で豊富な経験を持つ、国連人口基金東京事務所長の池上清子氏からは、武力紛争下と紛争後の女性への影響を取り扱った国連安保理決議1325号についての解説に続き、それに則して行われているUNFPAの活動の内容が紹介された。
コンサルタントとしてUNDPジェンダーチームとともに活動している斎藤万里子氏からは、UNDPの活動内容および組織内のジェンダー主流化の取り組み、そして危機予防・復興局がジェンダー視点を入れての活動を推進するために打ち立てた、「危機における女性の安全を確保・強化する」、「女性に届く公共サービスを提供する政府への変容」といった項目を含む、8ポイントアジェンダが紹介された。
本シンポジウムのコーディネーターでもある菅野琴氏からは、紛争、伝染病、環境問題、金融危機など、国境を超える危機が多発している現在の世界情勢は、国連に対する期待が高まる機会でもあるが、国連の普遍性・中立性に対して挑戦する勢力もでてきており、国連では活動現場の安全確保が大きな課題となってきているとの報告があった。また紛争と貧困の負の連鎖が諸問題の解決をより困難にしているが、支援の現場では、貧困・差別といった根本原因の解消に取り組むか、それとも目の前の危機への対応を優先するのかというジレンマがあるという。
これに続く質疑応答では、ジェンダー課題に取り組みに際しての国連内各機関の棲み分けや、国連組織とNGO組織、其々の特徴と相互連携、機能強化についての質問が出されたほか、東日本大震災の復興支援も話題となり、参加者にとって、国連機関の在り方や役割について再考し、かつその活動を身近なものと感じる機会となった。
《開催詳細》
【日時】2011年5月18日(水)17:00~19:45
【会場】お茶の水女子大学本館135号室カンファレンスルーム
【タイトル】公開シンポジウム「危機における国連機関の役割と戦略的ジェンダーの視点
(「国際社会ジェンダー論」連続講座第4回)
【講師】池上清子(国連人口基金東京事務所長)「国連人口基金におけるジェンダー関連課題の諸局面」/斎藤万里子(元国連開発計画(UNDP)職員、ジェンダーと開発コンサルタント)「国連開発計画のジェンダー平等戦略と8ポイント・アジェンダ」/菅野琴(元ユネスコ職員、お茶の水女子大学客員研究員)「人道支援か能力開発か?国連機関の葛藤」
【コーディネーター】菅野琴(元ユネスコ職員、お茶の水女子大学客員研究員)
【司会】舘かおる(お茶の水女子大学)
【参加者数】22名
2011/5/31掲載 |

池上 清子

斎藤 万里子

菅野 琴

会場風景
|
このページのトップにもどる
映画『女と孤児と虎』上映会×トークイベント
日本による植民地支配から冷戦下という軍事色の濃い歴史を背景に、韓国から欧米に養子縁組のため送り出された「コリアン・ディアスポラ」。彼らの「語り」に焦点をあてた映画、『女と孤児と虎』の上映会が開催された。本上映会では、映画が持つ時間的・空間的スケールの大きさや一貫したフェミニスト視点、そして製作者の真摯な思いが、会場からの大きな共感を呼び、日本での上映会のために来日したジェーン・カイスン監督とガストン・クン共同制作者は大きな手ごたえを感じていた様子であった。映画上映の後、コメンテーターの池内靖子氏からはフェミニスト美術批評の視点からのコメントが出され、徐阿貴氏からは映画の社会背景としてコリアン・ディアスポラの歴史解説があった。また、カイスン監督とクン氏を交えたトークもあり、韓国研究やディアスポラ研究、ヴィジュアルアートなど幅広い分野の研究者の参加を得て、盛況な催しとなった。
《開催詳細》
【日時】2011年4月30日(土)13:30~17:00
【会場】お茶の水女子大学共通講義棟2号館102号室
【上映作品】『女と孤児と虎』(The Woman, The Orphan, and the Tiger)、2010年、72分
【講師】ジェーン・ジン・カイスン監督/ガストン・ソンディン・クン共同制作者
【コメンテーター】池内靖子(立命館大学)/徐阿貴(お茶の水女子大学)
【司会】徐阿貴(お茶の水女子大学)
【通訳】本山央子(アジア女性資料センター)/臺丸谷美幸(お茶の水女子大学博士後期課程)
【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
【共催】女と孤児と虎』日本上映実行委員会
【後援】アジア女性資料センター/女たちの戦争と平和資料館(wam)/「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW-NET)/日本映画大学
【参加者数】83名
2011/5/20掲載
|

カイスン監督/クン共同制作者

池内 靖子

会場風景
|
このページのトップにもどる

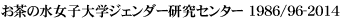

 3月6日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室にて、2011年度ジェンダー研究センター研究報告会が開催されました。研究報告会はIGS研究協力員による研究成果および計画の発表を柱とし、議論をたたかわせることで、今後の研究展開に資するとともにセンター教員、関係者そして研究協力員間の交流を推進することをねらいとしています。
3月6日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室にて、2011年度ジェンダー研究センター研究報告会が開催されました。研究報告会はIGS研究協力員による研究成果および計画の発表を柱とし、議論をたたかわせることで、今後の研究展開に資するとともにセンター教員、関係者そして研究協力員間の交流を推進することをねらいとしています。 公開ワークショップは、本学教員・舘かおるとAIT教員・日下部京子による、本学とAITの大学間学術交流協定やAITワークショップについての説明を含む挨拶から開始しました。これに続く、フィリップ・ドニー、日下部京子のAIT教員2名からの、タイ・ラオスにおける「災害とジェンダー」事例報告は、災害発生時のジェンダー課題についての基本的な問題を再確認する内容でした。履修院生による報告では、高田千尋が東日本大震災の被災地支援における企業の活動を取り上げ、スタンナード・ポリーは被災地のセクシャル・マイノリティ支援に目を向けるなど、先端的な課題に焦点が当てられています。AIT院生サムディ・タン、佐々木忍のタイ大洪水に関する報告は、入手の難しい細かいデータをまとめての分析となりました。加えて、被災地の女性支援に取り組むみやぎジョネットの八幡悦子氏からは、被災体験や被災地状況、避難所の現実、支援活動状況などを含む、被災地のジェンダー課題についての生の声が届けられました。コメンテーターの池田恵子氏からは、個々の報告についての丁寧なコメントと合わせて、院生達の今後の研究の展開を期待する激励の言葉が贈られました。
公開ワークショップは、本学教員・舘かおるとAIT教員・日下部京子による、本学とAITの大学間学術交流協定やAITワークショップについての説明を含む挨拶から開始しました。これに続く、フィリップ・ドニー、日下部京子のAIT教員2名からの、タイ・ラオスにおける「災害とジェンダー」事例報告は、災害発生時のジェンダー課題についての基本的な問題を再確認する内容でした。履修院生による報告では、高田千尋が東日本大震災の被災地支援における企業の活動を取り上げ、スタンナード・ポリーは被災地のセクシャル・マイノリティ支援に目を向けるなど、先端的な課題に焦点が当てられています。AIT院生サムディ・タン、佐々木忍のタイ大洪水に関する報告は、入手の難しい細かいデータをまとめての分析となりました。加えて、被災地の女性支援に取り組むみやぎジョネットの八幡悦子氏からは、被災体験や被災地状況、避難所の現実、支援活動状況などを含む、被災地のジェンダー課題についての生の声が届けられました。コメンテーターの池田恵子氏からは、個々の報告についての丁寧なコメントと合わせて、院生達の今後の研究の展開を期待する激励の言葉が贈られました。









 1月30日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室において、国際ワークショップ「東アジアにおける『女性と科学/技術』」が開催されました。本ワークショップは、2011年度IGS研究プロジェクト「『科学技術とジェンダー』に関わる研究の諸局面の検討」および、2010年度科学技術社会論・柿内賢信記念賞「アジアにおける女性研究者に関する科学社会論的研究」(受賞者:小川眞里子)の一環です。
1月30日、お茶の水女子大学学生センター棟第5会議室において、国際ワークショップ「東アジアにおける『女性と科学/技術』」が開催されました。本ワークショップは、2011年度IGS研究プロジェクト「『科学技術とジェンダー』に関わる研究の諸局面の検討」および、2010年度科学技術社会論・柿内賢信記念賞「アジアにおける女性研究者に関する科学社会論的研究」(受賞者:小川眞里子)の一環です。
















a.jpg) 7月4~16日、国連開発計画(UNDP)とお茶の水女子大学の共催による集中セミナー「ジェンダーとマクロ経済に関する能力構築」が埼玉県の国立女性教育会館において実施されました。
7月4~16日、国連開発計画(UNDP)とお茶の水女子大学の共催による集中セミナー「ジェンダーとマクロ経済に関する能力構築」が埼玉県の国立女性教育会館において実施されました。 梅雨の晴れ間となった6/4(土)、本学名誉教授・客員教授である戒能民江氏の講演会が開催された。冒頭挨拶に立った生活社会科学研究会会長の杉田氏からは、戒能氏が、ハラスメント問題等への取り組み等を通して大学の法リテラシーを高める推進力となってきたこと、21世紀COE「ジェンダー研究のフロンティア」の拠点リーダーとして学内のジェンダー研究・教育基盤強化の成果を挙げたことなど、着任以来の大学への貢献の数々が紹介された。これに続く講演は、大学学部時代に関わった「こつなぎ事件」闘争支援や「女子学生の会」の活動に始まり、1980年代の英国家族法の研究、DVやセクシャル・ハラスメントなど女性に対する暴力に関する研究等、これまで戒能氏が取り組んできた研究・活動の内容に加え、最近訪問してきた、東日本大震災被災地における女性グループの支援活動の様子にまで話が及んだ。1960年代以降の様々なレベルにおけるジェンダーと法のありようを振り返る内容となった。質疑応答では、多くの学生たちから、各々が向き合うジェンダー課題に関する質問などが出されたが、講演中で語られた、「あきらめない意思を持ち続ける」「あなたたちを尊重している女性たちがいる」という戒能氏の言葉は、これから社会へ出る学生をはじめ、戒能氏の後進となる若手研究者にとっても、困難に立ち向かう際の拠り所となるであろう。
梅雨の晴れ間となった6/4(土)、本学名誉教授・客員教授である戒能民江氏の講演会が開催された。冒頭挨拶に立った生活社会科学研究会会長の杉田氏からは、戒能氏が、ハラスメント問題等への取り組み等を通して大学の法リテラシーを高める推進力となってきたこと、21世紀COE「ジェンダー研究のフロンティア」の拠点リーダーとして学内のジェンダー研究・教育基盤強化の成果を挙げたことなど、着任以来の大学への貢献の数々が紹介された。これに続く講演は、大学学部時代に関わった「こつなぎ事件」闘争支援や「女子学生の会」の活動に始まり、1980年代の英国家族法の研究、DVやセクシャル・ハラスメントなど女性に対する暴力に関する研究等、これまで戒能氏が取り組んできた研究・活動の内容に加え、最近訪問してきた、東日本大震災被災地における女性グループの支援活動の様子にまで話が及んだ。1960年代以降の様々なレベルにおけるジェンダーと法のありようを振り返る内容となった。質疑応答では、多くの学生たちから、各々が向き合うジェンダー課題に関する質問などが出されたが、講演中で語られた、「あきらめない意思を持ち続ける」「あなたたちを尊重している女性たちがいる」という戒能氏の言葉は、これから社会へ出る学生をはじめ、戒能氏の後進となる若手研究者にとっても、困難に立ち向かう際の拠り所となるであろう。






