IGS通信2013
- 2014.1/25 国際シンポジウム「変動期の東アジアにおけるジェンダー主流化―現状と新たな挑戦」
- 11/9,10 AITワークショップ報告会
- 5/29 公開シンポジウム「サステイナビリティとジェンダー:科学と人類の未来を担う新たなパートナーシップを求めて」
国際シンポジウム「変動期の東アジアにおけるジェンダー主流化―現状と新たな挑戦」
1月25日、東京国立近代美術館講堂にて、国際シンポジウム「変動期の東アジアにおけるジェンダー主流化―現状と新たな挑戦」が開催されました。このシンポジウムは、2008年グローバル経済危機以降に、アジアを取り巻く変化、その反作用として誕生している保守主義的な政党支配の中におけるジェンダー主流化の現状を、各国の歴史的背景を踏まえつつ考察することを目的としています。シンポジウムは、台湾、韓国、ベトナム、日本の研究者による報告、2人のディスカッサントからのコメント、会場から各報告者への質疑応答の3部構成で行われました。
*シンポの様子は「クオータ制を推進する会」のニュースレターvol.4でも取り上げられています。 |
----------------------------------------------------------------------------------------------- 《開催詳細》 【日時】2014年1月25日(土)12:30-16:30 【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究センター 《 2014/3/11掲載 》 |
AITワークショップ報告会
2013年11月9、10日、微音祭において本年度のAITワークショッププログラムの総まとめとなる報告会が行われました。 AITワークショップは、本学博士前期課程とアジア工科大学大学院(Asian Institute of Technology)が主催する交換研修プログラムです。今年度、本学からは、開発・ジェンダー論コース生4名、地理環境学コース生1名の合計5名が、タイで行われるフィールド調査とワークショップに参加。研修テーマは、参加生の修論テーマと関連付け、「Global Justice, Women’s Health, and Prostitution」とされました。 今年はより多くの方にAITワークショップを知っていただきたいという思いから、微音祭で報告会を実施する運びとなりました。ワークショップ参加学生5名が企画・準備をし、マルシェ内のブースにて2日間に計4回、報告を行いました。 |
|
報告は、参加学生がバンコクとチェンマイで実施したフィールド調査結果に重点を置いて行われました。一例として、タイにおけるセックスワーカーへの支援、教育を行っているNGO団体EMPOWER(Education Means Protection Of Women Engaged in Recreation)での調査について報告がありました。セックスワーカーが語学や性感染症予防などについて楽しく学べるよう工夫された施設をスライドで紹介し、セックスワーカーへのインタビュー調査では、調査者に対するプライバシーに配慮する必要があったことを報告しました。バンコクやチェンマイでの観光や、AIT学生との交流の様子もスライドで紹介され、会場は終始和やかな雰囲気でした。 微音祭での報告会ということもあり、本学学生のみならず、開発・ジェンダー論コースに入学を希望する方、タイに関心がある方など、学外からの参加を得ました。微音祭での公開報告会は初の試みでしたが、AITワークショッププログラムの締めくくりというだけではなく、学内外にプログラムの魅力を広報する貴重な機会となりました。 |
----------------------------------------------------------------------------------------------- 《開催詳細》 《 2013/11/26掲載 》 |
公開シンポジウム「サステイナビリティとジェンダー:科学と人類の未来を担う新たなパートナーシップを求めて」
ジェンダー研究センターでは、2012年より、「サステイナビリティ」をテーマに研究プロジェクトを進めている。同年5月に実施した公開シンポジウム「『原発』とサステイナビリティ・サイエンス」では、チェルノブイリの経験をもとに、福島の原発事故の被災状況、特に、若者や子どもの健康や心理的影響、リプロダクティブ・ヘルスの問題を様々な角度から考察し、さらに「持続可能な地球のための科学」の観点からの提言も行った。その後の研究会では「サステイナビリティ・サイエンス」や核廃棄物管理に関する国民的議論を目指す熟議民主主義についての理解を深め、「サステイナビリティ・サイエンス」と「ジェンダー」という2つの研究領域の連関点を探る考察を進めた。2013年1月には国際シンポジウム「災害、復興におけるジェンダー公平性を問う」において、インドネシアからのゲストを迎え、インドネシアのアチャにおける実践事例を取り上げ、復興後社会の再構築にあたり、ジェンダー視点を取り入れることの重要性や、災害という経験が、単なる復旧ではなく、よりよい社会、よりジェンダー公平な社会への復興を目指す起点となる可能性があることも確認した。 |
菅野琴による報告「持続可能発展教育/ESD ユネスコ世界会議の動向とジェンダー視座からの論点」では「持続可能な開発」の基本概念の紹介とその後の国際社会における変遷を論じた。特に、その基本概念の適用主軸が「環境」にシフトし、グリーン化、ブルー(海洋)化への転換が始まる経緯が説明された。また、教育による「エンパワメント」により、女性が男性と共に自由意志で選択し、変革の主体となって行動できるようになることが確認された。持続可能な社会構築への挑戦は、「家族や労働のあり方や豊かさを支える男並みを基準とする社会システム」の枠組みの見直しも必然的に伴うとして、ジェンダーと持続可能性の接点を探った。
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------- 《開催詳細》 《 2013/7/31掲載 》 |

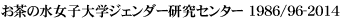

 はじめに、司会の申琪榮IGS准教授からシンポジウムの趣旨説明がなされました。昨今、アジアの国々では保守政権に戻り、世界的な新自由主義は金融危機以降も強く残っている。これらの変化は平等政策としてジェンダー主流化の取り組みにどのような影響を及ぼしているのか。各国のジェンダー主流化に関わってきた方々の報告を聞き、ジェンダー主流化の現状と課題を考察することが本シンポジウムの目的であることが確認されました。
はじめに、司会の申琪榮IGS准教授からシンポジウムの趣旨説明がなされました。昨今、アジアの国々では保守政権に戻り、世界的な新自由主義は金融危機以降も強く残っている。これらの変化は平等政策としてジェンダー主流化の取り組みにどのような影響を及ぼしているのか。各国のジェンダー主流化に関わってきた方々の報告を聞き、ジェンダー主流化の現状と課題を考察することが本シンポジウムの目的であることが確認されました。  黄長玲氏(国立台湾大学)による報告「不安定な連携:台湾の保守政権とジェンダー主流化」は、台湾の革新的な政権の下におけるジェンダー主流化と、現政権である保守政権の下におけるジェンダー主流化とを比較した上で、特に台湾の保守政権下における国家フェミニズムの動きについて報告がなされました。台湾では、2002年にはジェンダー主流化が台湾の政策に導入され、台湾政府内でジェンダー政策マシナリーが設置されました。2008年には保守政権である国民党が政権を奪還しましたが、これまで活躍したフェミニスト活動家が多く活躍し、ジェンダー主流化の流れは止まっていないとのことでした。台湾では国会議員の割合がアジアで2番目に高い一方で、派遣労働者の女性が多く、同姓婚については法案が反対されるなど、ジェンダー平等に関する課題が山積していることが確認されました。
黄長玲氏(国立台湾大学)による報告「不安定な連携:台湾の保守政権とジェンダー主流化」は、台湾の革新的な政権の下におけるジェンダー主流化と、現政権である保守政権の下におけるジェンダー主流化とを比較した上で、特に台湾の保守政権下における国家フェミニズムの動きについて報告がなされました。台湾では、2002年にはジェンダー主流化が台湾の政策に導入され、台湾政府内でジェンダー政策マシナリーが設置されました。2008年には保守政権である国民党が政権を奪還しましたが、これまで活躍したフェミニスト活動家が多く活躍し、ジェンダー主流化の流れは止まっていないとのことでした。台湾では国会議員の割合がアジアで2番目に高い一方で、派遣労働者の女性が多く、同姓婚については法案が反対されるなど、ジェンダー平等に関する課題が山積していることが確認されました。  金京姫氏(韓国中央大学校)による報告「ジェンダー主流化再考―韓国を事例として」は、韓国のジェンダー主流化の手法のうち、ジェンダー影響評価とジェンダー平等予算のイニシアティブを取り上げ、韓国のジェンダー主流化政策の実践、ジェンダー主流化の制度的特徴と結果について検証を行いました。韓国では2000年代に展開されたジェンダー主流化が「ジェンダー主流化のテクノクラート化」という現象を引き起こしていることが指摘され、その結果、女性を経済発展のための道具とみなし、女性に対する構造的な差別はなくならなかったことを指摘しています。フェミニスト理念に基づいたジェンダー平等を再び政策決定過程で焦点化するためには、ジェンダー主流化を、変革をもたらす意識的戦略として理解する必要があり、政策過程におけるフェミニストの関与がこれまで以上に重要になることを強調しました。
金京姫氏(韓国中央大学校)による報告「ジェンダー主流化再考―韓国を事例として」は、韓国のジェンダー主流化の手法のうち、ジェンダー影響評価とジェンダー平等予算のイニシアティブを取り上げ、韓国のジェンダー主流化政策の実践、ジェンダー主流化の制度的特徴と結果について検証を行いました。韓国では2000年代に展開されたジェンダー主流化が「ジェンダー主流化のテクノクラート化」という現象を引き起こしていることが指摘され、その結果、女性を経済発展のための道具とみなし、女性に対する構造的な差別はなくならなかったことを指摘しています。フェミニスト理念に基づいたジェンダー平等を再び政策決定過程で焦点化するためには、ジェンダー主流化を、変革をもたらす意識的戦略として理解する必要があり、政策過程におけるフェミニストの関与がこれまで以上に重要になることを強調しました。  ルオン・トゥ・ヒエン氏(ベトナム ホーチミン国家政治行政学院/WiPPA)による報告「ベトナムにおけるジェンダー政策:その実績と課題」では、ベトナム国内におけるジェンダー主流化の経緯と課題が提示されました。近年、ベトナム政府は法制度や政策におけるジェンダー平等の推進を行っていますが、依然として男性優位の家父長的な価値観や文化、慣行が根強く残っているため、ジェンダー格差は縮まっていません。一方、政府や政治の高いレベルにおいて男女平等を達成することも重要な目標に位置づけられていますが、党及び政府の最高意思決定機関における女性の占める割合は非常に低いとの指摘がありました。こうした状況への解決策として、各省庁の地方レベルにおいて女性の地位向上委員会が近年設置され、中央レベルにおいてもジェンダー平等やジェンダー主流化を推進する労働・傷病兵・社会問題省を設置しているということが紹介されました。
ルオン・トゥ・ヒエン氏(ベトナム ホーチミン国家政治行政学院/WiPPA)による報告「ベトナムにおけるジェンダー政策:その実績と課題」では、ベトナム国内におけるジェンダー主流化の経緯と課題が提示されました。近年、ベトナム政府は法制度や政策におけるジェンダー平等の推進を行っていますが、依然として男性優位の家父長的な価値観や文化、慣行が根強く残っているため、ジェンダー格差は縮まっていません。一方、政府や政治の高いレベルにおいて男女平等を達成することも重要な目標に位置づけられていますが、党及び政府の最高意思決定機関における女性の占める割合は非常に低いとの指摘がありました。こうした状況への解決策として、各省庁の地方レベルにおいて女性の地位向上委員会が近年設置され、中央レベルにおいてもジェンダー平等やジェンダー主流化を推進する労働・傷病兵・社会問題省を設置しているということが紹介されました。  三浦まり氏(上智大学)による報告「新自由主義的母性:2000年以降の日本の労働・家族政策」では、日本では、90年代に持ち込まれたジェンダー主流化の流れが2000年代の保守政権の中で有効性が失われたこと、一方で「新自由主義的母性」政策という分裂症的な女性客体化政策が打ち出されたことが指摘されました。女性活用、母性活用は新自由主義、反動的保守主義の双方から必要とされ、いずれの政策も、彼らの目的のために女性を客体化する点で一致しています。こういった状況に対抗するには、国家家族主義、新自由主義両方に同時に対抗できるような論理を打ち立てていくこと、更には女性が主体性を取り戻すことが重要であるとしました。
三浦まり氏(上智大学)による報告「新自由主義的母性:2000年以降の日本の労働・家族政策」では、日本では、90年代に持ち込まれたジェンダー主流化の流れが2000年代の保守政権の中で有効性が失われたこと、一方で「新自由主義的母性」政策という分裂症的な女性客体化政策が打ち出されたことが指摘されました。女性活用、母性活用は新自由主義、反動的保守主義の双方から必要とされ、いずれの政策も、彼らの目的のために女性を客体化する点で一致しています。こういった状況に対抗するには、国家家族主義、新自由主義両方に同時に対抗できるような論理を打ち立てていくこと、更には女性が主体性を取り戻すことが重要であるとしました。  伊田久美子氏(大阪府立大学)から各報告者へのコメントは、女性運動とジェンダー政策の観点からなされ、その推進力の力強さを評価しました。その上で、日本では女性運動との連携が政策を動かしてきたとは言い難く、ナショナルマシナリーの展開においては、活発ではなかったことを指摘しました。更に特に地方は、政治の在り方が振り回される傾向にあること、地方政策レベルでは、90年代に推進されたジェンダー主流化のための政策が次々覆され、定着しているとはいえないとしました。
伊田久美子氏(大阪府立大学)から各報告者へのコメントは、女性運動とジェンダー政策の観点からなされ、その推進力の力強さを評価しました。その上で、日本では女性運動との連携が政策を動かしてきたとは言い難く、ナショナルマシナリーの展開においては、活発ではなかったことを指摘しました。更に特に地方は、政治の在り方が振り回される傾向にあること、地方政策レベルでは、90年代に推進されたジェンダー主流化のための政策が次々覆され、定着しているとはいえないとしました。  足立眞理子氏(IGSセンター長)からのコメントは、新自由主義の経済政策(グローバル化)は、常に裏側にネオコンサバティズム的な指向性とつながっていたとし、各国におけるジェンダー主流化の取り組みの強さ、保守政権下においてもジェンダー主流化推進が続く現状を評価しました。その上で、日本のマシナリー問題は、組織として予算の裏付けがなく、実効性乏しいとしました。更には、アジアの経済発展はジェンダー差別的に進むとし、その裏で国家家族主義も根強く残っていることを指摘しました。
足立眞理子氏(IGSセンター長)からのコメントは、新自由主義の経済政策(グローバル化)は、常に裏側にネオコンサバティズム的な指向性とつながっていたとし、各国におけるジェンダー主流化の取り組みの強さ、保守政権下においてもジェンダー主流化推進が続く現状を評価しました。その上で、日本のマシナリー問題は、組織として予算の裏付けがなく、実効性乏しいとしました。更には、アジアの経済発展はジェンダー差別的に進むとし、その裏で国家家族主義も根強く残っていることを指摘しました。  本シンポジウムは学内外から多くの参加者を得ましたが、質疑応答の時間には、岡崎トミ子氏(元男女共同参画特命担当大臣)や赤松良子氏(元文部大臣、現WIN WIN代表)から、ジェンダー主流化を推進する上での女性運動との連携についてコメントが寄せられました。このほかにもクォータ制導入やジェンダー平等へのバックラッシュに関する多数の質問が寄せられ、本シンポジウムテーマに対する関心の高さが窺われました。アジアにおけるジェンダー主流化の現状を考察し、各国の課題について改めて考える機会を得た貴重なシンポジウムとなりました。
本シンポジウムは学内外から多くの参加者を得ましたが、質疑応答の時間には、岡崎トミ子氏(元男女共同参画特命担当大臣)や赤松良子氏(元文部大臣、現WIN WIN代表)から、ジェンダー主流化を推進する上での女性運動との連携についてコメントが寄せられました。このほかにもクォータ制導入やジェンダー平等へのバックラッシュに関する多数の質問が寄せられ、本シンポジウムテーマに対する関心の高さが窺われました。アジアにおけるジェンダー主流化の現状を考察し、各国の課題について改めて考える機会を得た貴重なシンポジウムとなりました。  会場風景
会場風景
