IGS通信2014
- 2015 3/29 埼玉新聞に大木さんがインタビュー取材を受けた記事掲載
- 2015 2/18 第2回研究交流会「都市周縁からCBDへ:マニラの外貨獲得部門における女性労働と居住の変容」
- 『地方議会人』1月号に大木直子さん論考掲載
- 12/17 サンドラ・ハーディング講演会「ミスター・ノーウェアのあとに:フェミニストの客観性、そして科学的主体とは何か」
- 11/1 国際シンポジウム「サステイナビリティとジェンダー」
- 8/17-22 世界女性学会参加記
- 7/10 第1回「政党行動と政治制度」研究会「国際比較からみた国会審議の特色と問題点」
- 7/9 湘南学園高等学校 総合学習活動「ジェンダー」
- 7/3 第1回研究交流会「地方議会における女性の代表性:日本と韓国の比較」
- 6/3 証言を聴く会「フィリピン元日本軍「慰安婦」エステリータ・ディさんを迎えて」
埼玉新聞に大木さんがインタビュー取材を受けた記事掲載
2015年3月29日の埼玉新聞一面に、大木直子さん(2014年度IGS研究協力員)へのインタビューを含む、統一地方選挙関連の記事が掲載されました。インタビュー中、大木さんは、女性の政治参画の障害のひとつに現行の選挙制度の問題があることを指摘し、クオーター制導入検討も含む議論が必要と述べています。記事全文をお読みになりたい方は、ジェンダー研究所前の掲示板へ。 《 2015/4/16掲載 》 |
|
第2回研究交流会「都市周縁からCBDへ:マニラの外貨獲得部門における女性労働と居住の変容」
2015年2月18日(水)に2014年度第2回IGS研究交流会を開催。太田麻希子氏(IGS研究協力員/明治学院大学ほか非常勤講師)が「都市周縁からCBD(Central Business District)へ:マニラの外貨獲得部門における女性労働と居住の変容」と題する研究報告をおこなった。太田氏の専門は、人文地理学。報告では、フィリピン、マニラにおける近年の就業および空間構造の変化、そして不平等な都市開発の在り方がスラムにいかなるインパクトをもたらしたのかを検証した。太田氏は、現地調査の結果と先行研究・資料の検討をもとに、近年のマニラ首都圏、および同地域の交通利便性が低いスラムの女性の就業と世帯構造に焦点を当てた。そして、BPO(Business Process Outsourcing)産業の成長を背景に従来と異なる女性の雇用が増加したということと、調査地のスラムで都心部へ若年女性オフィスワーカーを送り出す世帯が観察されていることを指摘し、首都圏の産業構造の変容が都市周縁のスラムにも及び、従来の階層構造と女性の居住が変容しつつある可能性について考察した。フロアからは、階層上昇移動の要因や、今後の現地調査について質問がなされた。 (記録担当:平野恵子 IGS研究機関研究員)
【日時】2015年2月18日(水)17時~20時 《 2015/3/27掲載 》 |
『地方議会人』1月号に大木直子さん論考掲載
IGS研究協力員・大木直子さん執筆の「なぜ、日本の地方議会では女性議員が増えないのか」が、『地方議会人』2015年1月号の特集「女性が活躍する社会の実現」に掲載されています。地方議会に女性が少ない現状分析とその原因となっている選挙制度についての論考です。掲載号をジェンダー研究センターにご寄贈いただきました。センター内の雑誌書架に置きますので、是非お手にとってご一読下さい。 《 2015/1/27掲載 》 |
サンドラ・ハーディング講演会
「ミスター・ノーウェアのあとに:フェミニストの客観性、そして科学的主体とは何か」
12月17日にサンドラ・ハーディング氏(UCLA栄誉教授)を迎えて、「ミスター・ノーウェアのあとに:フェミニストの客観性、そして科学的主体とは何か」と題する講演会を開催した。氏は、第一波フェミニストとして、その業績が広く知られている。講演では、著書『科学と社会的不平等:フェミニズム、ポストコロニアリズムからの科学批判』(北大路書房)で展開された、フェミニスト視点からの科学と価値中立性に関する論が提示された。フェミニズム、ポストコロニアリズムなど、社会正義の運動にコミットする立場からの科学がもとめる客観性とは、そして科学的主体とは、どういうものか。価値中立性を謳う科学は、恣意性から切断可能であるという前提で議論されてきた。しかしながら、ハーディング氏によれば、これは、弱い客観性に過ぎない。支配的な価値なり政治的主張に沿った形での価値中立に過ぎず、結果として男性支配的な方向への科学実践の推進力となってきた。ここからハーディング氏が主張するのは、価値中立性を自覚した「強い客観性」である。他の学問、専門領域と有機的にリンクし、互いに排除しないスタンド・ポイント理論は、これまで「科学的である」とはみなされていなかった女性の生活や身体の問題に向かって、直接的に、そして政治的な接続可能性を含んでいる。以上の講演を受けて、社会調査法やアクションリサーチ、そして伝統的な知の生産制度からの脱却がいかに可能となるかといった政治的理論的な指摘や質問が熱心になされた。
(記録担当:平野恵子 IGS研究機関研究員) 《開催詳細》 【日時】2014年12月17日(水)15:00~17:00 《 2015/3/31掲載 》 |
|
国際シンポジウム「サステイナビリティとジェンダー」
|
|
2014年11月1日に国連大学ウ・タント国際会議場において、国際シンポジウム「サステイナビリティとジェンダー」が開催されました。同シンポジウムは、本年11月に、持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議が日本で開催されることにちなみ、ジェンダーの観点から「サステイナビリティ」を検討し、併せてESDに関わる教育の役割について考える機会とするため、お茶の水女子大学ジェンダー研究センターと、国連大学サステイナビリティ高等研究所が中心となり主催したものです。国内外から広く関心を集め、関係者も含めると約200名が参加しました。 [記録担当:佐藤美和(国際シンポジウム「サステイナビリティとジェンダー」事務局研究員)] |
報告ファイルがご覧いただけます。 午前の部 持続可能な開発のための教育(ESD)とジェンダー 「ポスト2014/2015年国際開発アジェンダとジェンダー課題」 午後の部 ジェンダーの視座を持った持続可能な社会にむけて
「〈不安〉から〈ヴィジョン〉へードイツ市民運動と福島との接点」 「震災におけるトラウマとジェンダー」 「小さな議会のエネルギー条例づくり~ 3・11後の取り組み」 「地域からのエネルギーシフトー3万人のまちからできること」 |
|
《開催詳細》 【主催】
《 2014/12/17掲載 》 |
|
世界女性学会参加記
The 12th Women’s World Congress-2014 (University of Hyderabad, India)に参加して
本学リサーチフェローの小川真理子さん(2012年度ジェンダー学際研究専攻学位取得)がインドのハイダラバード大学で開催された第12回世界女性学会に参加され、その報告を寄せて下さいました。 |
1.第12回世界女性学会の概要 [小川真理子(本学リサーチフェロー)] |
|
第1回「政党行動と政治制度」研究会「国際比較からみた国会審議の特色と問題点」
7月10日に、第一回「政党行動と政治制度」研究会が行われた。本研究会は2014年度に上智大学・三浦まり氏、東京大学・スティール若希氏、本学・申琪榮氏の3名を中心メンバーとして立ち上げられた研究会であり、そのスタートとして当センターと共催による講演会が開催された。 文責 大木直子(IGS研究協力員/本学ほか非常勤講師) 《開催詳細》 【日時】2014年7月10日(木)17:30~19:30 【主催】「政党行動と政治制度」研究会、お茶の水女子大学ジェンダー研究センター 《 2014/7/28掲載 》 |
|
湘南学園高等学校 総合学習活動「ジェンダー」
7月9日(水)に湘南学園高等学校の2年生4名がジェンダー研究センターに来所されました。フィールドワークを要件とする総合学習活動で6つあるテーマのうち、「ジェンダー」を選択された生徒さんたちです。 事前に寄せられた質問に沿って、はじめに「ジェンダーとは何か」について平野より説明をおこないました。続いて、大木氏より女性の社会進出、特に政治分野におけるジェンダー課題について日本を事例に講義がなされました。議会におけるセクハラ問題に焦点が当てられ、現政権が掲げる成長戦略で女性の活用が叫ばれるいま、政治分野における女性の「活用」の現状把握とその分析は、日本のジェンダー課題を考察する上で時宜にかなったトピックでした。講義の最中も多くの質問がなされ、生徒さんたちの真剣な取り組みがみられました。湘南学園高等学校2年生の皆さん、ご来所有難うございました。 (文責:平野) |
----------------------------------------------------------------------------------------------- 《開催詳細》 【日時】2014年7月9日(水)14:00~16:30 《 2014/7/17掲載 》 |
第1回研究交流会 「地方議会における女性の代表性:日本と韓国の比較」
7月3日にジェンダー研究センター第1回研究交流会が開催された。研究交流会は当センター研究協力員による研究成果発表を柱とし、議論をおこなうことで研究協力員各自の今後の研究に資するとともに、センター教員、関係者そして研究協力員間の交流促進を目的としている。 2014年度第1回は、日本と韓国の地方議会における女性の代表性をテーマとした共同報告がおこなわれた。制度変更による女性の代表性への影響を考察する本報告では、選挙制度の変更とクォータ制の導入が女性議員の量的増加にとって重要な要素となっている韓国の地方議会の事例が前半に、選挙区や定数の変化といった制度の変更がみられる日本の地方議会の事例が後半に取り挙げられ、制度変更による女性の代表性への肯定的、否定的な影響の両側面が明らかにされた。 報告に対し、雑賀氏は、制度変更への女性運動の関わりを指摘した。また申氏は、比較研究にあたっての共通項と差異を指摘し今後の研究展開への期待を示した。フロアからは、制度変更に加えて制度が変化する際の政治的・社会的背景について言及がなされ、報告者との活発な議論のやり取りがおこなわれた。 地方議会レベルでの女性の代表性に焦点を当てる比較研究、特にアジアを事例とした先行研究は非常に少なく、今後の研究展開が待たれる興味深い成果報告であった。 (文責:平野) |
----------------------------------------------------------------------------------------------- 《開催詳細》 【日時】2014年7月3日(木)18時00分~20時30分 《 2014/7/15掲載 》 |
証言を聴く会「フィリピン元日本軍「慰安婦」エステリータ・ディさんを迎えて」
フィリピンより元日本軍「慰安婦」のエステリータ・ディさんをお迎えして、証言を聴く会を開催した。
(ジェンダー研究センター研究機関研究員、平野恵子) 《開催詳細》 【日時】2014年6月3日(火)13:20-15:00 【主催】第12回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議実行委員会 《 2014/6/20掲載 》 |
|

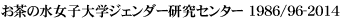




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)








 エステリータ・ディ氏
エステリータ・ディ氏

